最短20秒で一括見積依頼!
実績のある地元の優良業者を
ご紹介いたします。
archive
住宅の雰囲気を良くしたい、空間を広く見せたいといったときに有効なのが植栽です。
雰囲気作りだけでなく目隠し等にも使えますし、何年も継続して成長を楽しむ事ができます。
エクステリアの最後の仕上げとして植栽をしてみてはいかがでしょうか?

業者にもよりますが、一本あたり1万円弱、それに作業費用をプラスした値段になるようです。作業費用は本数にあまりよらず、本数が多ければ割引というサービスを行っている業者もあります。
相場としては、一般的な植栽一式で10円〜20万円といったところでしょうか。あくまで目安ですが、ホームセンター等で売っている樹木の2倍程度の値段で植えることができる、というのがあります。
適正価格かどうか不安な場合は複数の業者から相見積もりをとって比較するとよいでしょう。

出典:http://www.various-gardens.com/
まずはどういった目的で植栽をするのかを決めましょう。植栽には以下のような効果がありますので、参考にしてください。

日差しのきつい夏場等には庭に木陰を作りたいものです。植栽ならば日光を優しく遮り快適な空間にしてくれますので、テラスやデッキ周り等くつろぎのスペースにおすすめです。
外からの目線を遮りたい時も植栽が使えます。なるべく枝葉が密生した樹木が多く使われ、フェンスなどを使う場合よりも見栄えの良さの面で効果的です。

花壇でハーブを育てる、庭にミカンの木を植えるなど、実際に食べる物として植栽を楽しむ方も増えています。こまめなお手入れや虫・鳥対策などが必要ですが、収穫できた時の喜びはひとしおでしょう。

出典:http://www.sunlife-ex.co.jp/
花や実、葉の形等楽しみ方は様々です。春に花をつけるなら桜、秋の紅葉を楽しみたいならモミジなどが定番ですが、他にも様々な特徴を持った樹木がたくさんありますので探してみてはいかがでしょうか?いくつか植えて四季折々に移ろいゆくお庭にするのも素敵ですね。

出典:http://uekiya.cocolog-nifty.com/
外との境界や目隠しとしても有効な生垣。隣家との境では低木がおすすめです。自治体によっては町並みの緑化政策として助成金が出る場合もあります。
植栽をするにあたり、前述のような用途に合わせて樹木の種類を決める必要があります。

常緑樹とは1年を通して常に葉をつけている樹木で、対して落葉樹は冬場に葉を落とします。そのため、目隠しとして使用するならば常緑樹を選びましょう。
しかし、四季による葉の色の移り変わりは落葉樹の方が楽しめます。木陰作りとしては、冬場には日光が入るようになる落葉樹がおすすめです。

出典:http://www.garden-shales.jp/
字面の通り、広葉樹は桜などの葉が広く大きな樹木、針葉樹は松などの葉が細い樹木です。目隠し用ならば広葉樹の方が良さそうです。
デザイン面でも大きく変わってきますので、住宅と合った方を選びましょう。
樹木によって最大の高さはある程度決まってきます。これ以上は高くなってもらうと困る、等の条件がある場合はこちらも考慮すべきです。

これも樹木によって大体決まっています。横に広がるのか、細長いのか、三角形の形に葉をつけていくのか等…
それによって植える間隔も変わってきますので、注意が必要です。

光合成によって栄養を作っているので、基本的に植物は日照を必要とします。しかし、中には半日陰を好む樹木もあり、日照が少ない庭でも育てる事ができます。植える植物がどんな環境を好むかも考えてあげる必要があるでしょう。

シンボルツリーとは、その名の通りその家のシンボルとなる樹木です。家の雰囲気がぐっと良くなりますし、紅葉したり花や実をつけるものにしたりすれば見た目も華やかです。
子供が生まれた時に植え、その子とともに成長していくシンボルツリーにするという方もいらっしゃいます。
少しだけ人気のシンボルツリーをご紹介しましょう。
アオダモ
5〜6月頃に白い花を咲かせます
ハナミズキ
桜が終わった頃に一斉に開花しますく
ヤマボウシ
6〜7月頃に白い花を咲かせます
ミモザ
3〜4月頃に黄色い小花をたくさん咲かせます
ノリウツギ
アジサイの仲間、8月頃に白い花を咲かせます
イロハモミジ
10月〜12月にかけ黄色から真っ赤に紅葉します
カツラ
ハート形の葉が10月〜11月頃に黄色に色づきます
ブルーベリー
春は実をつけ、秋は真っ赤に紅葉します
シモツケ
11月頃から徐々に赤く紅葉していきます
ツリバナ
10月に実を付け、11月頃紅葉します
自分の家だけでなく、町並みの緑化にも貢献できる植栽。樹木の種類はとても豊富なので、目的に沿ったものが必ず見つかるはずです。
お手入れの問題等も考えつつ、家の外観や家族の好みに合った植栽を行いましょう。


住宅のイメージに直結する玄関周りのエクステリア。中でも表札やポストは日常的に使うものであり、重要なポイントの一つです。
昔は没個性なものが多く見られましたが、最近では住宅のスタイルの多様化にも伴いいろいろなタイプの商品が増えてきています。
では、住宅の顔ともいえる表札・ポストの選び方はどのようにすれば良いのでしょうか。少し見ていきましょう。

門柱・門扉・ポスト・表札などをセットで設置する事が多く、業者によってはセット価格として安くなっている場合もあるようです。 どのような部品にするかによって値段は前後しますが、一般的な工事ですと15万円〜30万円程度が相場でしょう。
工期は、これもまちまちですが5日〜20日程度かかることが多く、1ヶ月はかからないというのが普通です。

各メーカーで取扱っているものは、表札とポスト、それにインターホンがセットになっているのが一般的です。そして、そのタイプにはいくつか種類があります。

出典:http://www.atlas-home.co.jp/
門柱、壁、塀等に埋め込んで設置するタイプです。
その構造上、門等のプランニングの時から検討する必要があります。
柱にポストボックスを乗せた形で、比較的設置しやすいポールタイプのものが近年人気を集めています

既存の門柱や塀に取り付ける形で設置できるタイプです。
投函しやすい高さにすることや周りの外構とデザインを合わせることなどを注意しましょう。
埋め込み型に比べ設置が容易ですが、その分取り外しもしやすいので防犯対策が必要です。

据え置き型と同じく後から設置が可能ですが、好きな高さに引っ掛けることができるため据え置き型に比べて場所を選びません。これも簡単に取り外す事ができてしまうため、ポストに鍵をかけるなどの工夫をしましょう。

ポールの上部にポストが乗っているタイプのものです。アメリカンスタイルとも呼ばれ、門扉が無い玄関にも合いますし、門扉と組み合わせる事も可能です。

前項でも少し触れましたが、ポストには防犯機能も必要です。投函された手紙が盗まれ、個人情報が流出してしまうケースは珍しくありません。 ポストのデザインを考える時は、見た目だけでなく防犯の面も検討しましょう。
どのようにポストを選べば良いか?
まず重要になってくるのがポストの大きさです。最近ではメール便などの大型郵便物も増え、ポストが小さいとはみ出てしまう事があります。当然外から盗まれてしまいやすく危険です。良く扱う郵便物の大きさを考えた上で、ポストの大きさを決めましょう。
次に投函口を考えましょう。ポストは大きければ良い訳でもなく、投函口が大きすぎるとそこから手を入れ郵便物を取られてしまう可能性があります。簡単に手が入らないような形状になっているかどうかがポイントです。
取り出し口には鍵を付けた方が無難です。そして、ポストは毎日開け閉めするものなので鍵の使い易さが大切です。お子様でも簡単に解錠でき、荷物や傘で片手が塞がっている時でも操作しやすいものを付けるべきでしょう。

出典:http://www.keihangreen.com/
他にも門柱にあれば便利な機能はいくつかありますのでご紹介します。

出典:http://my-point.cocolog-nifty.com/
機能が多様化してきているドアホンですが、やはり外の様子が肉眼で確認できるカメラ機能があると良いでしょう。モノクロとカラーがありますが、夜間ですとモノクロの画像では見辛いのでカラーのものがおすすめです。
夜間の防犯・安全面で欠かせないのが玄関周りの照明です。表札やドアホンを照らすものやアプローチ部分を明るくするフットライトなど様々なものがあるので、用途に合わせて使い分けましょう。自動で点灯してくれるタイマー機能やセンサー機能もあります。

運送業者との不在表のやり取りが煩わしい方にはおすすめです。門柱に埋め込むタイプのものを使えば大きさを気にしなくて済みます。
ここまで簡単に門柱の外構工事に関する知識をご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?
玄関周りは来訪者がいらっしゃった際に最初に目にする部分であり、いわば住宅の顔です。さらには家族がほとんど毎日使うため、見た目のデザインだけでなく使い易さも重要になってくる、プランニングが難しい場所です。
自分だけではなかなかイメージがわかない場合は、ショールームや友人のお宅などを参考にし、家族のライフスタイルに合った機能を持つプランにしましょう。


会社名:株式会社 アセンティア
電話番号:048-532-0377
FAX番号:048-532-0288
創業: 13年
社員数:7人
対応エリア:埼玉県北中部~群馬県南部
営業時間:AM8:30~PM6:30
定休日:日曜日
住所:埼玉県熊谷市川原明戸515
会社名:アメイジングスペース 株式会社
電話番号:028-612-8560
FAX番号:028-612-8045
創業: 2018年5月
社員数:3人
対応エリア:栃木県全域、一部対応(群馬県、茨城県、千葉県、福島県)
営業時間:AM10:00~PM5:00
定休日:日曜日、祝日
住所:栃木県宇都宮市宝木本町1144-20
WEBサイト:https://amazingspace.co.jp/
あなたの家に門はありますか?大きな門や小さな門、扉のついている門やついていない門などその形状や素材は豊富にあります。
外構のデザイン上、門は家の顔ともいえる存在です。門を検討する場合は、家全体の雰囲気や外観のバランスを考慮しつつ設置の必要性の有無を検討する必要があります。
このコンテンツでは、外構を検討する際に門扉や門柱を含む門選びの手助けとなる情報をご紹介します。

大きさや仕上げによって変動しますが、門まわりは総額、15万円~30万円ほどで工事を行う人が多いです。
もちろん工事業者によってデザインや機能といった提案内容が異なるので、費用だけで考えるのではなく、トータルで最適な提案を選ぶのがおすすめです。

門まわりは外構スタイルによってデザインパターンが異なります。
近年人気の高いオープンスタイルでは、門扉を設置しない開放的な入り口にします。門柱のみ設置し、そこにポストや表札を置きます。
クローズドスタイルでは門柱と門扉をともに設置し、家の敷地と外をしっかり遮断します。重厚感のある門まわりにすることもあれば、閉鎖的な感じを和らげるタイプもあります。
門まわりの外構工事・エクステリアを考える際に重視するポイントは
・使いやすさ
・防犯性
・デザイン性
の三つになります。
門扉の基本的な機能は「防犯性を高める」「プライバシーを保護する」といった点が挙げられます。門柱には表札やポストの設置場所としての機能があります。
これらをトータルで考えて、自分の家や周囲の環境に合った門まわりの外構工事を行うといいでしょう。

門の中心とも言うべき門扉にはいくつか種類があります。主に開き方と素材・材質の二つに分けて考えられます。まずは開き方の種類を解説します。

イメージしやすい一般的な門扉になります。左右のバランスがよく、見栄えのいいのが特徴ですが、ある程度幅がないと設置が困難です。

扉は二つあるものの、大きさが均等ではないタイプです。片方の門の開け閉めで通行が容易なので、使い勝手がいいです。

扉が一つしかないため、横幅が狭い門にも設置できます。

奥行きが狭い場合に有効なのが引き戸です。横幅は必要になりますが、段差やレールのないタイプにすればバリアフリーな設計も可能です。

次に門扉の素材・材質を紹介します。

耐久性があり、軽いのが特徴でコストパフォーマンスがよく、一般家庭で広く使われています。
アルミ形材とは成形の方法が異なります。溶かしたアルミを型に流し込み、多彩なデザインを作り出せます。

天然木を素材としていて、軽くて丈夫です。庭園などの和風の外構とよくあい、高級感のある玄関となります。

比較的安価で手入れが簡単ですが、デザインによっては安っぽく見えてしまいます。木製に見えるような質感のものが人気です。

重厚感のある門構えに最適です。鉄という素材の特性上重く、防犯性も高いですが、開け閉めがしにくくなりやすいというデメリットもあります。

門まわりの外構工事を考えている方に注意してほしいポイントを紹介します。

門はあなたの家の顔ともいえる重要な部分です。家屋が純和風で、立派な庭園があるのに門だけ洋風だと違和感を覚えませんか?トータルでのバランスを考慮して門まわりの設計を行うのは重要です。
和風洋風はもちろん、開放的なオープンスタイルなのか、クローズドスタイルなのかで門扉を設置したり、設置しても簡易的なものにしたりしてバランスをとるとよいでしょう。

エクステリアを選ぶ際には、どうしてもデザインに目が行きがちですが、実用性も十分検討すべきです。例えば高齢の方がいる場合は大きな段差のない門まわりにし、門扉も軽いもののほうがよいでしょう。
赤ちゃんがいる場合はベビーカーが通れる幅を確保できるかを考えるべきです。実際に生活することをイメージして、不便だと感じないものを作りましょう。

外構のなかでも特に門まわりは、周囲からよく見られる部分です。その街の景観を作っている一部だという認識をもつことも重要です。
周りの家とまったく同じものを取り入れる必要はありませんが、都心部の住宅地などでは景観を崩さないような配慮を持った方がよいでしょう。
門まわりの外構工事を行う際の基礎知識を、主に門扉を中心に紹介しました。エクステリア・外構工事は大きな買い物となるので、十分に検討すべきです。 特に門まわりでは
・使いやすさ
・防犯性
・デザイン性
の3つのポイントに分けて考えることで、あなたの満足のいく外構工事ができるのではないでしょうか。



株式会社こんぐみ設計事務所 一級建築士事務所 代表取締役 今 琢摩
一級建築士登録 第367808号
設計事務所、ゼネコン、内装施工会社等勤務を経て、株式会社こんぐみ設計事務所 一級建築士事務所を設立。
その時そこにしかないベストな空間を目指し、小さなプロジェクトでも大きな視野を忘れず、大きなプロジェクトでも小さな視点を忘れず、お客様のために全力を込めて当たることをモットーとする。
東京理科大学理工学部建築学科 卒業
株式会社こんぐみ設計事務所 一級建築士事務所
一級建築士事務所 埼玉県知事登録 (1)第11577号
https://kongumi.com/
戸建てのリビングに太陽の光を取り込みたい、室内で洗濯物を干したい、ペットの遊び場としてのスペースが欲しいという方におすすめなのがサンルームです。
リビングルームに隣接する形で設置するケースが多く、リフォームの際に増築する方が増えてきています。
このコンテンツでは、これからサンルームを検討されるという方に向けてサンルームを造る前に確認しておくべき事や基礎知識などを紹介いたします。

一般的な部屋の増築に比べ工事が簡単なため、費用も安く工期も短いです。相場としては50万円前後でしょうか。
大きさやメーカー・デザインの違い、オプションの機能を付けたりすることで価格は変動しますので、見積もりを良く見ることが大切です。
価格が適正かどうか不安な時は、複数業者の相見積もりを比較してから検討すると良いでしょう。


壁や天井がガラス張りの窓になっている部屋の事で、太陽光を多く取り入れる事ができます。
欧米等では住宅を建てる段階からプランニングし、建物の一部として設計する場合が多いですが、日本においては後から増築という形でリフォームするケースが良く見られます。
家族のくつろぎの空間やガーデニングのスペース、物干し竿を設置して洗濯物を干す等、その用途は様々です。

出典:http://www.clovergarden.biz/
窓や折戸を開放できないサンルームには、枠が固定されているがゆえのメリットとデメリットがあります。(開閉できるタイプをサンルームと呼ぶ場合もあります)
メリット
まずはなんといっても日当りの良さでしょう。全面のガラス窓から日光が降り注ぎ、開放的な空間が生まれます。ひなたぼっこやくつろぎスペースとして最適です。
さらに、雨の日も家事が可能です。サンルームは温度が上がりやすく、雨の日でも洗濯物が良く乾きます。また、高い気温を好む植物等も育てる事ができるでしょう。
サンルーム内は冬でも日光が降り注ぎ暖かいです。また、部屋を増築するということで内側のリビングルームの暖房効率も上がり、暖まりやすくなるでしょう。結果的に光熱費の節約になります。
デメリット
いい事ばかりではありません。全面ガラス張りなので夏はとても暑いです。サンルームの方角にもよりますが、夏の日光対策は考えておくべきでしょう。
さらに、南向きではない場合は冬場はかなり寒いです。簡易的な囲いテラス等ですと隙間風も吹き込み、寒さに拍車がかかります。
そして、定期的な手入れも必要です。やはり窓ガラスは汚れが目立ちやすく、放っておくとすぐにほこりやゴミが付着しみすぼらしくなってしまいます。天井のガラスもたまには掃除するべきでしょう。

出典:http://www.yutei-furyu.co.jp/
まずは主に何を目的として造るかを考えましょう。大きさは敷地の広さにもよりますが、例えば家族の憩いの場として使う予定ならばある程度の家具を置くスペースは必要になってきます。
続いてデザインですが、住宅との調和を取れるようなものにするべきでしょう。周りの景観とそぐわないデザインにすると浮いて見えてしまいます。主観的に考えすぎず、他の人の意見も聴いてみましょう。施工業者にパース図を見せてもらうことができれば直感的に完成後の見た目が分かります。
業者選びも注意が必要です。悪徳業者に任せてしまう事がないよう、ネット上の口コミや施工実績などを事前に調べ、できれば複数の業者の見積もりを比較しましょう。
サンルームを増築しようとしている方向けに基本的な知識を紹介してきました。大切な事は、
・パネルの開閉の有無など、建て方の違いを理解し、用途に合ったものを選ぶ。
・設置後の手入れや温度・湿度管理も考慮する。
・金銭のトラブル等が無いよう業者選びはしっかりと。
といったところでしょうか。
外構工事は一度造ってしまうと取り返しはなかなかきかないので、ショールームに行き商品を見るなどして慎重に決めましょう。施工業者に施工例を見せてもらうのも一つの手です。


趣味の場所として楽しむ方が多い”庭”という空間。一口に庭づくりといっても、コンセプトやデザインなどに様々な選択肢があります。
なかなか庭の造り直しというのは難しいので、なるべくイメージ通りのものを造り上げたいものです。
当コンテンツは、そんな庭作りを今まさに検討している方に向けて知っておきたい庭・ガーデン外構工事の基礎知識をご紹介いたします。

庭のリフォームには、
1.芝生や砂利を敷く等基礎的な工事
2.サンルームやウッドデッキ等新しい設備を設置する工事
3.庭全体を造り変える工事
の3種におおまかに分けられます。では、それぞれ費用はどれほどかかるのでしょうか。

1平米あたりの値段で計算する業者が多いです。
どのような工事をするかにもよりますが、例えば芝生を敷く工事ですと材料費と施工費を合わせて1平米あたり6000円〜1万円程度でしょう。
既存のものを撤去してからの工事になると、別途撤去費用がかかる場合があります。

何を設置するかによって大きく変わります。サンルームならばそのものの値段+施工費用、ウッドデッキやテラスならば1平米あたりの値段で決まるでしょう。
ただ、大半の工事は50万円〜100万円程度で収まるのではないでしょうか。

荒れ果ててしまった庭の全体リフォーム、新築の戸建てに庭を造る工事等が当てはまります。大掛かりかつ様々な素材を使うため、100万円は超えてくるでしょう。
予算オーバーにもなりやすいので、その場合資金と理想の妥協点を見つけなければなりません。

まずは庭づくりに取りかかる上で注意すべきポイントを紹介していきます。

庭づくりにおいて、テーマはとても重要です。洋風にするのか和風にするのか、はたまた和洋折衷のスタイルにするか…
それによって植える植物や置くインテリア等が決まってきますので、ガイドラインとしても庭のテーマは初めに決めておきましょう。

テーマももちろん大切ですが、敷地の条件との兼ね合いがあってこそです。日当りや水はけ等を考慮しないと思うような植物を育てられませんし、敷地以上の大きさのプランニングだとそもそも不可能です。また、周囲の町並みと調和したデザインにする必要もあります。
簡易なものでもよいので、庭の図面に実際にプランを書き込んでみると分かりやすいでしょう。

住宅は数十年にわたり済み続けていくもの。庭のデザインを考えるにあたり、将来的なライフスタイルも考えておくと良いでしょう。子供の遊び場は造るのか、その子が成長したらどうするか、ペットは飼う予定なのかなどなど…
家族としっかり話し合い、具体的なイメージを固めましょう。

造ってしまえばそれで終わり、という訳にはいきません。庭は定期的にメンテナンスをしないと、すぐに草木が伸び放題になり汚く見えてしまいます。夏は雑草や虫対策、秋は落ち葉の清掃など四季に合わせての維持管理も必要です。
草木は成長が遅いものや落ち葉が少ない物にする、雑草が生えにくいよう砂利や防草シートを使用する、清掃しやすいよう石畳を敷く等が管理しやすい庭づくりのポイントです。

一般的に、住宅の建築費用の1割程度を庭の予算にかけるとちょうど良いと言われています。既存の樹木は再利用する等、必要に応じて節約しつつ庭作りをおこないましょう。

素材を選ぶにあたって、まず考えるのは建物や周辺環境との調和でしょう。和風の住宅なら和風の素材、洋風なら洋風の素材といった風に、周りと比べて浮いてしまわないようにすべきです。
また、耐久性や管理のしやすさも一緒に考えると良いでしょう。
以下に素材の例をいくつか示します。

洋風の住宅にぴったりの素材です。値段によって耐久性などに違いがあり、ガーデニングやアプローチなど長持ちさせたい場所に使うならば良く選んだ方がよいでしょう。
使い込めば経年とともに味が出てきますが、あまり積みすぎると重くなってしまうので注意が必要です。

出典:http://www.morizouen.co.jp/
コンクリートやブロックなどしっかりした基礎の上に敷いていくのが一般的です。デザインや大きさの種類が豊富で、どのような住宅にも合わせることが可能です。
駐車場などの仕上げが安っぽくなってしまった時のアクセントとしてもおすすめです。

レンガより若干値段が高めですが、その分高級感が増します。丈夫なので長持ちしますし、アプローチ部に敷くと雨でも滑りにくいです。
天然のもので厚さや大きさがまちまちな事がありますので、敷く際には割って大きさを調節しながらの作業になるかもしれません。
塀を造る積み材にはコンクリートブロックやレンガ等がありますが、塗り壁もおすすめです。
デザインが色々選べますし、値段もブロックなどとそれほど変わりません。塗り材によっては汚れが付きやすいものもありますので、よく確認しておきましょう。
塀にこだわりたい時はコンクリートがよいでしょう。型にコンクリートを流し込んで造るので形の自由度が高く、イメージ通りのものが出来上がります。
打ちっぱなしですと圧迫感があるので、塗ったり樹木と組み合わせると優しくなります。施工に必要な技術も高く、従って値段も少々お高めです。

外からの視線を優しく遮りたい場合に有効です。竹垣を使用すると和風なイメージになります。町並みの緑化にも一役買い、地域によっては緑化政策の一環として助成金が出る場合もあるので、確認してみてはいかがでしょうか。
いざ庭のリフォームをしようと思い立っても、まず何をすればいいか分からないのではないでしょうか。そこで大事なのは庭の理想像を持つ事です。
それによって使う素材や樹木等が決まってきますし、万が一予算がオーバーしそうな時も、ここは削っても良いがここは譲れない、などの折り合いも付けやすいでしょう。
納得のいく庭作りで、快適なガーデンライフをおくりましょう。


車1台の駐車スペースは約18㎡です。住宅敷地の中に駐車スペースをつくるとなれば、かなりの面積を占め、家の雰囲気にも影響を与えます。
今回は、地域の気候や家と調和するガレージやカーポートをつくるために知っておきたい種類と費用そして選び方までわかりやすく解説します。

ガレージとカーポートと駐車スペースには構造に違いがあります。まずは、それぞれの特徴やメリットとデメリットをお話しします。
ガレージとは、柱と壁と屋根のある建物です。車庫と呼ばれることもあります。メリットは、建物内に車を保管できるため、紫外線や風そして侵入者からも車を守ることができます。また、収納や電源、水回りの設備を設置することで作業場としても使うことができます。デメリットは、設置するスペースと費用がかかることです。
カーポートとは、柱と屋根で構成された駐車場です。壁はありません。メリットは、限られたスペースでも設置しやすいことと、費用が抑えられること、そして車の出し入れがしやすいことでしょう。デメリットは、壁がないためガレージと比べると耐久性が劣ることです。また台風のときには飛来物が車に直接あたる可能性があります。
駐車スペースとは、ただ単に車を駐車する場所を意味した言葉です。いわゆる屋外にある平置き駐車場のイメージです。メリットは、費用を最低限に抑えられることでしょう。また必要に応じてあとからカーポートやガレージにすることも可能です。デメリットは、車がむき出しになることです。屋根もないため紫外線が直接あたり塗装への影響があるでしょう。

参考URL「ヨドコウ ガレージ:ラヴィージュⅢ(シンプルなプレハブ使用ガレージ例)」:https://www.yodomonooki.jp/products/garage/ravige/
参考URL「garden stail.com(こだわりのガレージ例)」:https://garage-style.com/
ガレージの種類はたくさんあります。シンプルなプレハブ使用のガレージもあれば、もうひとつの戸建て住宅のようなこだわりのガレージまであります。また、ガレージには建物の中に駐車スペースを組み込むビルドインガレージもあります。
ガレージやカーポートのように構築物を設置する場合は、本体価格だけでなく施工費も別途かかります。施工費は基礎工事(コンクリート打設含む)や残土処理費、人件費などを含めて数十万円程度かかります。施工費が数万円の見積もりの場合は、単に設置だけの費用である可能性があり、内容の確認が必要です。シンプルなプレハブ使用のガレージを例にすると、本体価格が50万円だとしても施工費を加えると相当の総額になります。ログハウス調や内装にこだわったガレージの場合は、総額300万円以上になることもあります。
車のガレージは、固定資産税の対象になることがほとんどです。また建築確認申請が必要になることもあります。

カーポートは柱の構造によって2種類に分けられます。
参考URL「YKK 片側支持式カーポート」:https://www.ykkap.co.jp/consumer/products/exterior/frouge_first
左右の片側にだけ柱があるカーポートを片側支持式カーポートといいます。駐車スペースの左右に余裕がある場合に適しています。左右に余裕がないときには、後方に柱をたてる後方支持式カーポートもあります。
費用は本体価格と施工費などの諸経費をあわせた金額になります。片側支持式カーポートは、屋根の素材によって金額はかわりますが、おおよそ40~60万円が本体価格で施工費などが別途かかります。
参考URL「YKK 両側支持式カーポート」:https://www.ykkap.co.jp/consumer/products/exterior/frouge
左右両方に柱があるカーポートを両側支持式カーポートといいます。両側に柱があるため上からの力に強い構造です。2台以上のカーポートや豪雪地帯におすすめです。
費用は1台ならば本体価格が60~80万円、2台以上になると間口や屋根の高さによっては本体価格が100万円以上になることもあります。
ガレージには門扉が必要です。ここからは、ガレージの門扉の種類についてお話しします。
参考URL「YKK 伸縮式レイオスシリーズ」:https://www.ykkap.co.jp/consumer/products/exterior/rayos
伸縮式とは、レールやキャスターによって伸縮する扉が開閉する門扉です。もっとも多いものは、垂直パンダ方式とよばれるもので縦格子の組子を折りたたむ方式です。
参考URL「YKK 跳ね上げ式ルシアスシリーズ」:https://www.ykkap.co.jp/consumer/products/exterior/lucias-upgate
跳ね上げ方式は、電動もしくは手動で門扉が上に持ちあがります。左右にスペースがない場合に選ばれます。ただし、柱と本体の間に人が侵入できる隙間ができることがデメリットです。防犯性を高めるためには、隙間をふさぐ必要があります。
引き戸式は、伸縮式の伸縮しない門扉です。開くときに扉と同じ長さのレールが必要となるため一般の住宅では採用しづらいでしょう。
参考URL「YKK 電動シャッタータウンゲート」:https://www.ykkap.co.jp/consumer/products/exterior/town_gate2
シャッターは、防犯性に優れています。ただし、シャッターを設置するためには水平な地面が必要です。また、電動シャッターはシャッターを巻き上げる機械が上部にあるため、塀やフェンスよりも高さが高くなる傾向があります。
ガレージやカーポートには屋根があります。屋根の材質にはさまざまな種類があります。ここからは、屋根の材質別メリットとデメリットと費用についてわかりやすく解説します。
参考URL「三協アルミ」:https://alumi.st-grp.co.jp/products/select/carport/point05/
ポリカーボネート板は、アクリル板の30倍、ガラスの250倍もの強度があるといわれています。旅客機の窓やスーツケースなどにも使われています。
メリットは、紫外線と赤外線をカットできることです。紫外線ならばほぼ100%、赤外線は50%カットできるといわれています。また燃えにくい性質があり、色も豊富にあります。
費用は金属板(ガルバリウム鋼板)より安く抑えられる傾向があります。
屋根の材質は、ポリカーボネート板もしくは金属板で悩むことが多いでしょう。金属板はガルバリウム鋼板が多く使われます。メリットは耐久性が高いことです。費用はポリカーボネート板より高くなります。
カーポートの金属板といえばガルバリウム鋼板でしたが、建築基準法が改正されてアルミニウムも構造材として認められました。防火地域などでカーポートに防火性が求められる場合におすすめです。
参考URL「オンデュリン 屋根材オンデュビラ」:https://www.onduline-shop.com/products/detail/16
カーポートの屋根は意外と目立ち、家の印象に影響を与えます。「もっと個性的な屋根がいい」という場合は、屋根材にこだわってみるといいでしょう。例えば、フランス製の「オンデュビラ」は、欧州規格をクリアした耐久性があります。緑や赤などカラフルな色もあり個性的なカーポートに仕上がるでしょう。
ガレージやカーポートは使い勝手と防犯性が重要です。失敗しないポイントは4つあります。
1つ目は、敷地に対応するガレージやカーポートを選ぶことです。例えば門扉を選ぶとき、傾斜地ならば選べる門扉はとても限られます。2つ目は防犯性です。隙間がなく高さがあるほうが防犯性は高まります。3つ目は使い勝手のよさです。高齢者が使うならば、門扉を手動で動かす伸縮式よりも電動のシャッターや跳ね上げ式のほうが便利ではないでしょうか。4つ目はコスパとデザインです。ガレージやカーポートも家と同じようにメンテナンスが必要です。一時的な出費だけでなく長期的なコスパも考えることが大切です。
ガレージやカーポートは、隣家と接するため雪が多い地域は屋根から落ちる雪が隣家の敷地に入らない配慮も必要です。ガレージやカーポートの設置は、地域の気象条件や関連法規に詳しい業者を選ぶことも大切なポイントです。


門をくぐるとすぐに玄関がある家と、玄関までの道のりがある家、どちらに魅力を感じますか?門扉から玄関までの道を玄関アプローチと言います。訪問客が必ず通る場所ですし、玄関周りは初めに目に入る、第一印象を決める重要な場所となります。 「おしゃれな家」「きれいな家」といった良いイメージをもってもらうには、外構としての玄関アプローチとデザインが非常に重要となります。玄関アプローチの外構工事を行う際に知っておくべき基礎知識をご紹介します。



出典:http://sakauedesign.blogspot.jp/
玄関扉をあけたときに、道路から中が見えてしまうと、あまりいい気はしません。門扉の正面に玄関を置くのは避けたほうがよいでしょう。また、トイレや浴室といったプライベートな部屋の近くを通らないような設計にするのも重要です。音やにおいで不快な思いをさせないようにしたいところですが、避けられない場合は植え込みなどでうまく目隠しをしてあげるとよいでしょう。















株式会社こんぐみ設計事務所 一級建築士事務所 代表取締役 今 琢摩
一級建築士登録 第367808号
設計事務所、ゼネコン、内装施工会社等勤務を経て、株式会社こんぐみ設計事務所 一級建築士事務所を設立。
その時そこにしかないベストな空間を目指し、小さなプロジェクトでも大きな視野を忘れず、大きなプロジェクトでも小さな視点を忘れず、お客様のために全力を込めて当たることをモットーとする。
東京理科大学理工学部建築学科 卒業
株式会社こんぐみ設計事務所 一級建築士事務所
一級建築士事務所 埼玉県知事登録 (1)第11577号
https://kongumi.com/
塀やフェンスには、道路と隣家の境界線だけでなく、目隠しや防犯の役割もあります。ひと昔前は、塀といえばブロック塀、フェンスといえばシンプルなアルミ製が一般的でした。しかし今は「圧迫感のない目隠しフェンス」「災害に強いフェンス」など付加価値のあるフェンスが登場しています。
今回は、建物をより引き立てつつ、しっかりと目隠しできるフェンスの種類と費用、そしてそれぞれのメリットとデメリットをお話しします。

目隠しフェンスの役割は、道路や隣家からの「視線をさえぎる目隠し」と敷地内から見える「敷地外景色をさえぎる目隠し」の2つです。道路や隣家からの視線はとても気になるものです。また、敷地内から見える敷地外の景色を調整することで自己領域(プライベート空間)を意識することができます。
さらにフェンスには、不審者の侵入や建物の保護、建物や植栽を引き立てる背景としての役割もあります。住人が目隠しフェンスにどのような役割を求めるかによって、選ぶフェンスの種類も変わります。

目隠しフェンスには、さまざまな材質やデザインがあります。また、求める役割によっては高さや構造も変わります。
ここからは、目隠しフェンスの代表的な種類と費用の目安を紹介します。費用は戸建住宅(40坪130㎡、周囲約46mを囲う場合)を想定しています。材料費から工事費、人件費などすべての費用を加味した金額ですが、物価上昇と人件費高騰により相場が算出しづらくなっています。外構工事をする場合は、複数社から見積もりをとり比較検討することをおすすめします。
敷地を囲う塀やフェンスとして使われるもので、よくみかけるものがコンクリート製のブロック塀ではないでしょうか。広く流通している理由は、ずばり材料が豊富にあることと加工や施工が簡単にできること、そしてコストの安さです。ブロックの種類は、グレーの建築用コンクリートブロックのほか化粧ブロックや左官仕上げのブロック塀もあります。ただ、最近はすべてをブロック積みにすることは少なく、ほとんどは低いブロック積みの上に軽量のアルミフェンスを設置します。下を重く上を軽くすることで、災害への安全対策にもなります。
ブロック積みフェンスの最大のメリットは、費用を安くおさえられることでしょう。デメリットは、正しい施工が必要なことです。ブロック塀の施工には、基礎コンクリートや鉄筋、控え壁など建築基準法に定められた構造規制があります。長く安全に使うためにも、正しい施工ができる業者選びが大切です。
最近は、コンクリート製のブロックではなく、軽量の樹脂ブロックも登場しています。硬質ポリスチレンフォームのパネルならば、見た目はブロック積みですが、控え壁なしで2.4mまで施工することができます。軽量になることで基礎工事も小さく済み、工期も短くすることができます。
参考URL「大林株式会社FIT WALL」:https://dairin-fit.jp/products/fit-wall/
RC造フェンスは、現場打ちコンクリートです。ブロック塀のように目地がないため、吹付けをすることでよりデザイン性の高い目隠しフェンスになります。 メリットは、構造的に安全性が高くオシャレな仕上がりにできることです。デメリットは、施工技術によって仕上がりに差が出ることです。また、工期が長く費用も高くなります。工期が長くなる理由は、コンクリートには養生期間が必要だからです。養生期間とは、型枠をはめたまま急激な温度の変化や雨風からコンクリートを守る期間です。RC造フェンスは、現場でコンクリート打ちを行います。1か月間の工期には、養生期間が含まれています。 RC造フェンスは、ブロック塀のように構造規制はありませんが建築物としての規制があります。
参考URL「三協アルミ 耐風圧フェンス」:https://alumi.st-grp.co.jp/products/gate/fence_alumi/reziria/
現在アルミフェンスは、もっとも普及している目隠しフェンスと言っても過言ではないでしょう。アルミフェンスには、直線的な模様のアルミ形材と曲線やデザイン性が高い鋳物(型に流して成型)があり、和風にも洋風にも対応することができます。以前は、鋳物は高価なイメージがありましたが、現在はアルミ形材と価格に差がなく使いやすくなっています。
メリットは、スチールフェンスのように錆びないことです。また、アルミフェンスは透過性が高いため、植栽と組み合わせることでオリジナリティある景観をつくることができます。とくに風が強い地域では、メッシュ状の耐風圧強度が高いアルミフェンスを選ぶことで倒壊のリスクを軽減できるでしょう。デメリットは、ブロック積みにアルミフェンスを取りつける場合の施工が難しいことです。目隠しフェンス自体が不安定にならないように正確な鉄筋の配置ができる業者を選びましょう。
参考URL「ディーズガーデン アルファウッドフェンス」:https://www.deasgarden.jp/product/gate/
樹脂フェンスは、木の粉と樹脂を混ぜて固めたつくられたものです。見た目は木製フェンスそっくりです。木製フェンスの高級感と樹脂のメリットを兼ね揃えたフェンスです。
メリットは、軽量であることと耐久性です。目隠しフェンスは、設置場所によって160cmほどの高さが必要になることもあります。樹脂フェンスは、軽量のため高さがあるフェンスも実現可能です。和風の建物や庭園には、生垣の代わりに樹脂でつくられた竹の御簾垣もおすすめです。御簾垣は、風通しよく目隠しをすることができます。
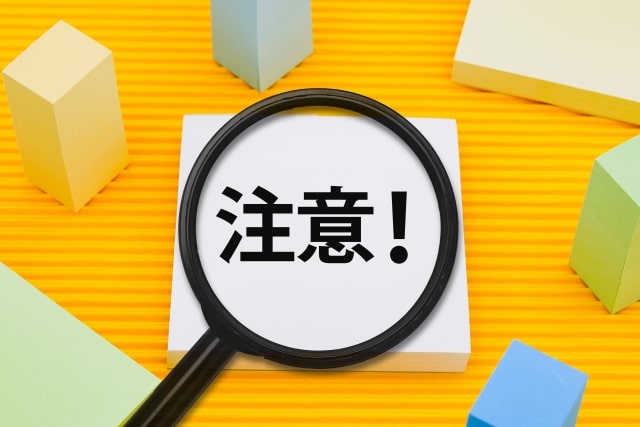
目隠しフェンスの費用は、設置する面積や全長と材質によって大きく変わります。また費用には、設置する工事費や人件費なども必要です。目隠しフェンスの費用は安くても数十万円、いい材質を選べば100万円以上かかります。「節約するためにDIYしたい」と考える人も多いのではないでしょうか。しかし、外構工事の中でもとくにフェンス設置は地域に合った材質と正しい施工が欠かせません。
目隠しフェンスの費用を節約するたった1つの方法とは、地域を熟知している業者かつ信頼できる業者を選ぶことです。地域密着の業者は、地域性や気候を熟知し、適した材質の目隠しフェンスを選ぶことができます。また、信頼できる業者は正しい施工と十分な養生期間を設けることで丈夫なフェンスに仕上げることができます。結果として、修繕やメンテナンスの必要が減り、長期的にみると費用を節約できることになるのです。
そして注意点は「業者によって費用は異なる」です。とくに材料費以外の工事費や諸経費は選ぶフェンスによっても変わります。設置が難しいフェンスは施工費が高くなります。複数社から見積もりをとり、納得できる見積もり内容の業者を選ぶようにしましょう。
自然災害が増え、外構に対する防災意識が高まっています。目隠しフェンスは、道路や隣家に接する外構であり、耐震性が高い材質やユニット型の工期が短い商品も誕生しています。「自分の家に適したエクステリアや外構がどういうものなのか」を外構のプロに相談してみてはいかがでしょうか。


複数業者に相見積りで
失敗しない外構工事を!
最短20秒で一括見積依頼!
実績のある地元の優良業者を
ご紹介いたします。