最短20秒で一括見積依頼!
実績のある地元の優良業者を
ご紹介いたします。
新居づくりでは、内装や設備ばかりに目が行きがちですが、家の印象を大きく左右する外構も同じくらい大切です。
「外構はいつごろから考えればいいの?」「家づくりの予算を優先したら、お金が足りなくなりそう…」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
実際、外構計画に手が回らず、引き渡し直前になって慌てて業者を探した結果、間に合わなかったり、想定外の予算オーバーになったりするケースは少なくありません。
そこで今回は、新築外構工事を進める最適なタイミングと、一連のスケジュール・チェックリストをまとめました。余裕をもって計画するポイントを押さえれば、「完成したらイメージと違った…」という後悔を防ぎ、理想の暮らしをスムーズにスタートできます。
結論としては、住宅の建築着工と同じ時期(引き渡しの3~6か月前)から外構計画を動かすのが理想的です。
このタイミングだと、家の間取りや外観のテイストを踏まえながら、じっくり外構デザインを検討できます。例えば、駐車場の広さや庭の植栽、フェンスの高さなどを建物の設計と合わせて計画すれば、家全体に統一感を持たせることが可能です。
逆に、引き渡し直前(完成1か月前)に慌てて外構業者を探すのは避けましょう。時間がないと十分な比較検討ができず、満足いく外構にならなかったり、引っ越しまでに工事が間に合わないリスクが高まります。
また、完成後にゆっくり考える手もありますが、その間は庭や駐車場が使えず生活に不便が生じます。
ベストは住宅工事と並行して早めに計画を進め、遅くとも引き渡し2~3か月前までに外構プラン・見積もりを依頼し、1~2か月前には契約を済ませておくことがポイントです。
ちょっとしたエピソード
知人のAさんは、新居の打ち合わせで設備や内装に予算を注ぎすぎてしまい、外構を先送りにしていたそうです。完成1か月前になって外構の見積もりを取りに行ったところ、想定より高額で驚愕…。さらに、複数社を検討する時間もなかったため、工事が引き渡し日に間に合わず数週間遅れてしまったとか。
「最初から外構費用も含めて予算を組んでおけばよかった」と、今でも後悔しているそうです。
家づくり全体の流れの中で外構工事のタイミングをつかむため、まず住宅本体工事と外構工事のスケジュールを押さえておきましょう。両者を並行して計画することで、建物と外構の完成時期を揃えやすくなります。
工期は順調に進めば着工から約4~6か月程度ですが、プラン内容で変動します。
全体でおよそ2~3か月を見ておくとよいでしょう。住宅工事の進捗や天候によって前後する場合もありますが、建築会社と外構業者が連携することでスムーズに進められます。
ここからは、外構工事を失敗なく進めるための具体的な手順を、時系列でチェックしていきましょう。計画初期の予算確保から引き渡し後のフォローまで、漏れなく進めるための全工程チェックリストもご紹介します。
家づくりの早い段階で外構に充てる予算枠を確保します。
目安として外構費用は平均100万~300万円程度と言われますが、希望する内容や敷地条件で増減します。
内装などに予算を割きすぎて外構が削られる事態を避けるため、最初から建築予算の中に外構費を組み込みましょう。
「家が完成したのに外構費用が残っていない!」とならないよう、少し多めに見積もっておくのがポイントです。

家の間取りや外観デザインが固まったら、外構の大まかなイメージを膨らませます。
門扉や駐車場の配置、庭の使い方など、家族のライフスタイルに合った要望を書き出してみましょう。将来車を買い替える予定があれば駐車スペースは大きめにする、ペットや子供の遊び場が必要なら芝生エリアを作る…といった具合に数年先を見据えて計画することも大切です。
家と外構のデザインに統一感を持たせるため、建物の外観テイストや色にマッチする素材・植栽を選ぶよう意識します。
この段階では雑誌や施工事例を見て「やりたい外構」の方向性を固めておき、プラン作成に備えます。
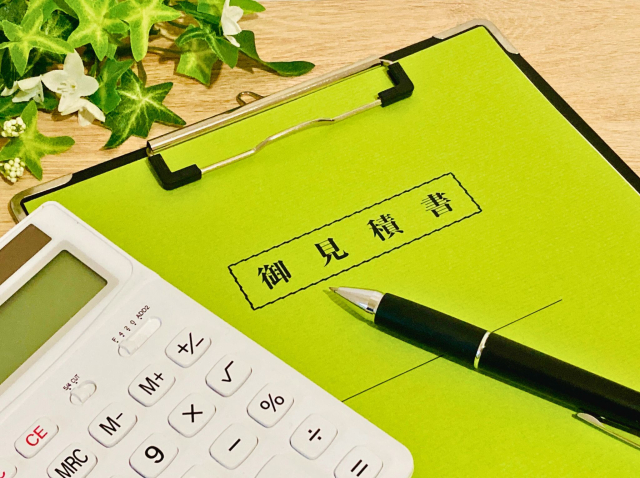
住宅の工事が始まるころ(引き渡しまで3~6か月前)を目安に、具体的に外構業者へプラン作成と見積もりを依頼します。
依頼先は2~3社程度に声をかけ、相見積もりを取るのがおすすめです。ハウスメーカー提携の業者を紹介される場合もありますが、費用や提案内容を比較するためにも複数社検討しましょう。
業者選定の際は実績や施工例、営業年数や保証内容などもチェックポイントです。候補を絞ったら早速問い合わせを行い、建物の図面一式や要望リストを渡して現地打ち合わせを依頼します。
プラン提案書や見積書の完成には通常1~2週間程度かかるため余裕を持って依頼しましょう。
なお、建物の基礎工事が完了してからの方が地面の高さや配置が明確になり、より正確な外構プランを作成できます。
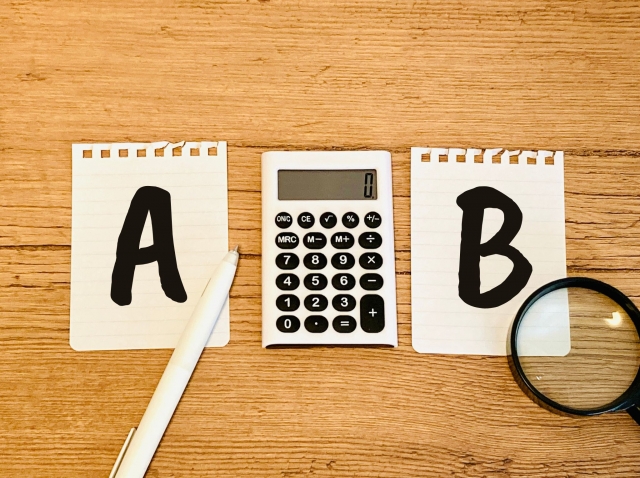
提案が出揃ったら、各社のプランと見積もりをじっくり比較検討します。
デザイン面では家との調和や使い勝手、将来のメンテナンス性などをチェック。費用面では総額だけでなく見積もり内訳が明確か、単価が適正かも確認します。
使用する素材や製品の品名・型番が具体的に記載されているか、不明瞭な項目はないかも重要です。疑問点があれば遠慮なく質問し、納得のいくまでプランを練り直してもらいましょう。
「相見積もり中」であることを伝えておくと、各社競争意識からサービスしてくれる場合もあります。複数社から提案を受けている旨を適切に伝え、より充実した内容や価格交渉に臨みましょう。
外構プランと施工業者が決まったら契約を交わします。
契約時期は建物完成の1~2か月前が理想的で、この頃までに契約しておけば建物工事との調整や資材手配もスムーズです。
契約内容として工事範囲・仕様・金額・支払条件・工期を再確認し、不明点は全てクリアにします。
特に見積書では追加工事発生時の対応や費用について明示があるか、施工後の保証期間・アフターサポート体制が明記されているか確認してください。
契約書類にサインする前に、図面と見積もりの内容が食い違っていないか最終チェックし、納得したうえで締結しましょう。
いよいよ外構工事スタートです。
建物の基礎工事が終わった段階からであれば、外構工事を並行して進めることも可能です。
一般的な外構工事の施工期間は約2~4週間程度ですが、規模によって変動します(門扉や塀がないオープン外構なら1~2週間、フェンスや門で囲うクローズ外構は3~5週間ほどかかる例もあります)。
引き渡し日に外構も完成させるには、建物完成の少し前から着工し並行作業するのが理想です。スケジュールについては建築会社とも綿密に調整し、職人さんの動線がぶつからないよう配慮します。
着工後に変更したい点が出てきた場合、対応自体は可能でも追加費用や工期延長のリスクが伴うため、気づいたことは早めに業者に伝えることが大切です。
工事が完了したら、最終確認を行います。図面どおりに施工されているか、門扉や照明の動作、植栽の状態などを施主自身でもチェックしましょう。
業者立ち会いのもと問題がないことを確認できたら引き渡しとなります。使い方の説明やメンテナンスのアドバイス(植木の水やり方法やコンクリート養生期間の注意など)を受け、保証書や今後の連絡先を受け取ります。
これで晴れて家も外構も完成し、新居での生活を気持ちよくスタートできます。
| チェック項目 | 内容 | チェック欄 |
|---|---|---|
| 家族のライフスタイルを整理したか? | 車の所有台数、子どもやペットの有無、将来的な生活の変化も含めて整理 | □ |
| 駐車スペースの数とサイズを検討したか? | 軽・普通車、将来的に大型車や来客用スペースが必要かを検討 | □ |
| 庭やアプローチの使い方をイメージしたか? | ガーデニング、子どもやペットの遊び場、くつろぎ空間など | □ |
| 希望の外構テイストを絞り込んだか? | ナチュラル/モダン/和風など、建物との統一感を意識 | □ |
| 外壁や屋根など家の外観との色合わせを意識したか? | 外構素材の色や質感が家とマッチしているか確認 | □ |
| フェンスや門柱など必要な設備をリストアップしたか? | 必要・不要を明確にし、防犯やプライバシーの観点も加味 | □ |
| 希望する植栽やシンボルツリーのイメージを持ったか? | 四季の彩り・メンテナンスの手間も考慮 | □ |
| 参考になる事例を収集したか? | SNS・施工例サイト・雑誌などで好みの外構イメージを収集 | □ |
外構の検討を住宅計画と同時並行で早期に始めておくことには多くのメリットがあります。
「外構は後でいいや…」と後回しにしてしまうと、以下のようなデメリットやリスクが生じる恐れがあります。
こうした理由から、外構を後回しにすると「予算」「プラン」「暮らしやすさ」「安全性」の面でマイナスが生じる可能性が高まります。どうしても引き渡しまでに間に合わなかった場合は、焦って不完全な工事をするより、一旦入居してから改めて依頼し直した方が良いとも言えます。
次に、もし引っ越し後に外構工事を行う場合、どんな点に注意すべきかを補足します。
さまざまな事情で新居引き渡し後に外構工事を行う選択もありえます。実際、全国的には「入居後ゆっくり外構を考えた」という方も少なくありません。引っ越し後施工には以下のようなメリットとデメリットがあります。
まとめると、引き渡し後の外構工事は「生活ニーズを反映できる」反面、「完成までの不便」や「デザイン統一の難しさ」があると言えます。やむを得ず後回しにする場合でも、上記デメリットを踏まえて計画・業者選定を行えばリスクを減らせます。
例えば、最低限のアプローチや駐車場だけは先に施工しておく、防犯上必要なフェンスだけは仮設でも設置しておくなど、段階的に整える方法も検討しましょう。
外構工事は依頼する季節によっても進み具合が変わります。日本の四季それぞれの特徴と、工事に適したタイミングを押さえておきましょう。
人気の春・秋は外構業者の繁忙期でもあるため、希望の時期に着工したいなら早め早めの問い合わせと予約が肝心です。季節要因も考慮に入れて、ベストなタイミングで依頼しましょう。
最後に、外構計画をより良いものにするためのコツや注意点をまとめます。タイミング以外にも押さえておきたいポイントに目を通し、失敗のない計画づくりに役立ててください。
外構は家の見た目や使い勝手を補完する存在です。設計段階から建物と外構をトータルでプランニングし、後からチグハグにならないようにしましょう。
具体的には、敷地内の配置計画時に駐車場やアプローチ位置を決めておく、住宅の確認申請前に外構の概要プランも固めておくなどが理想です。
地域によっては景観条例などで着工前に外構計画の提出が求められる場合もあるので、必要な手続きも視野に入れておきましょう。
給排水のマスやガス管の引き込み位置など、敷地内には動かせない設備が存在します。一度決まった配管・マスの位置は基本変更できないため、そこに支障のない外構プランを考える必要があります。
例えば排水マスの上に階段やカーポート柱を配置しない、どうしても近くに設けるなら点検スペースを確保するなどの配慮が必要です。事前に建物図面でこうした要素を把握し、業者とも情報共有しておきましょう。
駐車場サイズの例のように、ライフスタイルの変化に耐えうる柔軟な外構にしておくと安心です。
家族が増えた時の車両台数、自転車置き場の拡張、将来子どもが独立して庭をリフォームする可能性…さまざまなシナリオを想像し、余白や拡張性のあるレイアウトにしておくと便利。
電気自動車用コンセントや宅配ボックスを将来的に導入予定なら、あらかじめ配線やスペースだけ確保しておくのもおすすめです。
予算や時間に限りがある場合、すべてを一度に完璧に仕上げようとせず、優先度の高い部分から施工する方法もあります。
例えば生活必需の駐車場・アプローチ・フェンスは先に作り、ウッドデッキや庭造りは後日追加する計画にすれば初期費用を抑えられます。自治体の補助金・助成金制度も要チェック。
地域によってはエクステリアの緑化やバリアフリー改修などに対して補助金が出るケースがあります。高齢者向けのスロープ設置補助などもあるので、居住地域の最新情報を確認しましょう。
外構の出来は業者の腕に左右されます。価格だけでなく提案内容や実績にも目を向け、信頼できるプロを選ぶことが大切です。
判断基準としては、営業年数や施工事例、資格・コンテスト受賞歴、保証内容、問い合わせ対応の丁寧さなどが挙げられます。
特に直近の施工例はその業者の得意分野やデザインセンスが分かるので、公式サイトやSNSなどをチェックしてみてください。複数社に相談し相性を見極めるのもポイントです。
提出された見積書は細部まで確認しましょう。工事内容ごとの明細が明確か、安価な材料に変更されていないか、保証期間やアフターサービス内容はどうか、増減費用の取り決めはあるかなどがポイントです。
疑問点は遠慮なく質問し、書面に残してもらうことで後々のトラブルを防ぎます。工事後の定期点検やメンテナンスについても事前に確認しておきましょう。信頼できる業者であれば説明も丁寧にしてくれます。
新築外構工事を満足いく形で仕上げるには、「いつ動き出すか」というタイミングがとても重要です。
ベストは住宅着工と同時期から準備を始め、引っ越しに間に合うよう余裕をもって進めること。早めの計画開始により十分な打ち合わせ時間を確保し、比較検討や調整を重ねることで、理想のデザイン・使い勝手・予算内で外構を完成させられます。
一方、遅すぎる着手はさまざまなリスクを招くと分かりました。資金計画や生活開始後の利便性まで見据え、できるだけ計画段階から外構にも目を向けておくのが得策です。
もし事情で後回しになっても、本記事で述べた注意点を押さえていれば大きな失敗は避けられます。
そして、外構工事の成功には信頼できるパートナー探しも欠かせません。複数の外構業者からプラン・見積もりを取り寄せて比較するのが理想ですが、自力で一社一社問い合わせるのが大変ならエクステリアコネクトの一括見積もりサービスの活用も検討してみてください。実績ある複数の外構業者をまとめてご紹介するので、提案内容や価格を簡単に比べられて便利です。
上手に活用しながら、安心かつ理想的な新築外構工事を実現しましょう。
外構まで含めてこそ完成する「あなただけの住まい」。ぜひ計画段階から外構にも目を向け、家族にとって快適で誇れる住環境づくりを進めてください。早めの準備と綿密なチェックリスト管理で、悔いのない外構を完成させましょう。


複数業者に相見積りで
失敗しない外構工事を!
最短20秒で一括見積依頼!
実績のある地元の優良業者を
ご紹介いたします。