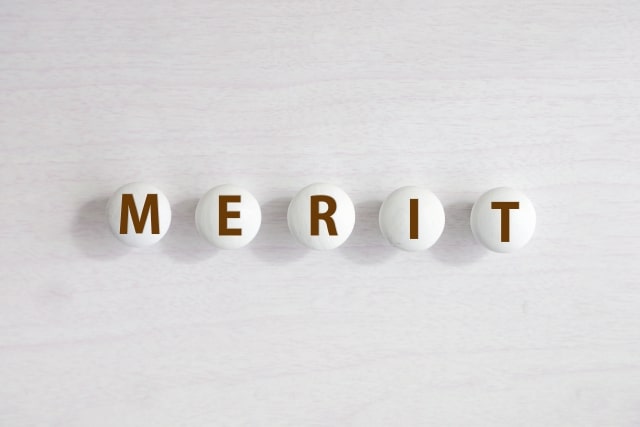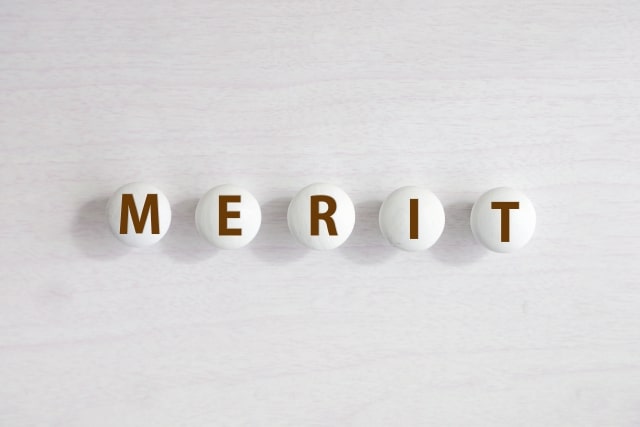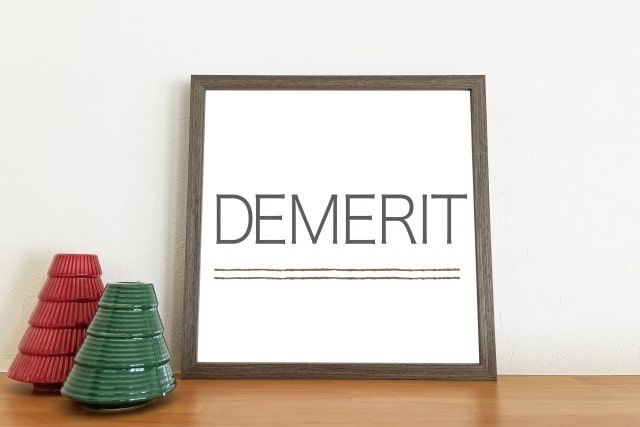「新築の建物は完成間近だけど、外構のことを後回しにしていて大丈夫?」
「予算や工事期間、補助金や施工後のトラブル対策も、まとめて知りたい!」
家づくりは内装や設備に目が行きがちですが、外構(エクステリア)も家の“顔”となる重要な部分。
本記事では、外構工事を検討するベストタイミングから、よくある失敗事例と回避策、費用相場や補助金制度、さらに見積もり時にチェックすべきポイントなどを幅広く解説します。
1新築外構工事のタイミングが重要な理由

外構は家の“顔”をつくる
- ・門柱や駐車場、フェンスなど、外構は住まい全体の第一印象を左右する重要要素です。
- ・デザインや機能を充実させることで、暮らしやすさと防犯性の両方を高められます。
家づくり全体の予算配分を左右
- ・早めに外構も視野に入れておくと、建物費用ばかりに資金を割きすぎず、バランスよく予算を配分できます。
- ・複数の業者を比較する時間も確保しやすくなります。
建物との一体感が出しやすい
- ・建物と同時進行で外構をプランニングすると、カラーや素材の統一感を取りやすいです。
- ・後から別途工事を行うより、やり直しや追加費用も抑えられます。
2外構工事を始める3つの代表的な時期とメリット・デメリット

新築外構工事の検討タイミングは、大きく3パターンに分かれます。以下のメリット・デメリットを踏まえて、最適なタイミングを見極めましょう。
| タイミング |
メリット |
デメリット |
| A:引き渡し1か月前に急いで動き始める |
- ・短期集中で業者が見積り・施工を進めてくれる
- ・なるべく引っ越しまでに間に合わせやすい
|
- ・打合せ時間が不十分でイメージ共有が不足
- ・予算不足で低品質になりがち
|
| B:引き渡し後にゆっくり考える |
- ・住み始めてから必要な箇所が分かる
- ・実際の動線や生活感に合わせてプランを練りやすい
|
- ・引っ越し後に工事するため生活導線に支障
- ・外観が未完成状態で過ごす期間が長引く
|
C:建物の着工が始まった頃から動き始める
(引き渡し3~6か月前) |
- ・建物図面や仕様が固まってから外構を詳細に計画
- ・スケジュールに余裕があり施工トラブルを防ぎやすい
|
|
結論:最もおすすめなのはCの「建物着工が始まった頃」。着工開始から引き渡しまで数か月あるため、業者選定やデザインの打合せをじっくり進められます。
3早めに検討するメリット
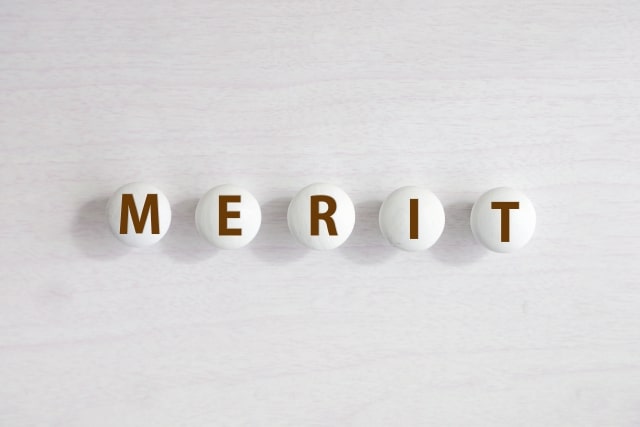
-
・じっくり考える時間が持てる
- 車の台数やウッドデッキの有無など、ライフスタイルに合わせた外構をしっかり検討できます。
-
・見積もりの比較・業者選びがしやすい
- 複数業者にプランを出してもらい、費用や提案内容を比較する余裕が生まれます。
-
・引っ越しと同時に外構も完成しやすい
- 駐車場・アプローチが整っていると、荷物の搬入もスムーズで快適に新生活を始められます。
4後回しにしたときのリスク
-
・打合せ不足による施工トラブル
- 時間がない中で決めると、「こんなはずじゃなかった…」という仕上がりになるリスクが高まります。
-
・予算不足で外構を妥協することに
- 建物本体に資金を使い切り、外構に十分な予算を回せなくなる場合があります。
-
・引っ越し後の生活に支障
- 工事が生活動線を塞いだり、防犯性が未整備のまま生活する時間が長引くことがあります。
5よくある失敗事例と回避方法
事例①:「駐車場スペースの寸法ミス」
- 失敗内容:新車のサイズに合わせて駐車場を計画したが、数年後に大きな車へ乗り換えたらスペースが足りなくなってしまった。
-
回避方法:
- 将来の車の買い替えや増車を想定し、横幅・奥行きともに少し余裕を持たせる。
- 駐車場の配置や出入口の幅も、車両のサイズ変化に対応できるよう計画する。
事例②:デザインの統一感がない
- 失敗内容:建物の外観と外構がチグハグで、全体的にバランスが悪い印象になってしまった。
-
回避方法:
- 家の外観(壁・屋根・サッシなど)と外構のカラー・素材・テイストを最初からトータルでプランニングする。
- 設計段階でイメージ画像やサンプルを使い、色味・質感をきちんと確認する。
6外構工事の施工期間と費用相場
6-1. 一般的な工事期間の目安
-
オープン外構:塀や門扉のない開放的デザイン
-
クローズド外構:フェンスや門扉で敷地を囲むスタイル
-
セミクローズ外構:部分的に塀やフェンスを設置
※敷地の広さや天候、業者の状況によって変動します。
6-2. 設備別の施工期間と費用目安(詳細版)
| 設備・工事内容 |
施工期間の目安 |
費用相場(目安) |
| カーポート |
1~2週間 |
約20~50万円 |
| ウッドデッキ |
1~2週間 |
約30~70万円 |
| フェンス設置 |
1週間前後 |
約10~40万円 |
| 人工芝設置 |
1~3日 |
約10~30万円 |
| 照明設置 |
1~2日 |
約5~15万円 |
7利用できる補助金・助成金制度
-
地方自治体による外構工事補助金
- 条件を満たすと10万~50万円程度の補助が出ることも。
- 居住地域の役所や自治体ホームページで最新情報をチェック。
-
バリアフリー工事助成制度
- 高齢者や障がい者がいる家庭向けに、スロープ設置や段差解消などの費用を助成する制度がある場合も。
- 要件や助成額は自治体により異なるため、事前確認が必要です。
8見積もり取得時のチェックリスト
- ・見積り項目ごとの明細が明確か
- ・使用する素材や製品名が具体的に記載されているか
- ・保証期間や内容が明記されているか
- ・施工後のアフターサポート内容がわかるか
- ・追加工事が発生した場合の費用や対応方法が明示されているか
9新築外構工事Q&A
Q:外構工事費用は住宅ローンに含められますか?
A:建物と同時進行であれば、住宅ローンに含められる場合があります。ただし、引き渡し後に別で工事をする場合は対象外となるケースもあるため、金融機関や施工業者に相談してください。
Q:工事中に変更は可能ですか?
A:可能ですが、追加費用や工期延長のリスクがあります。変更の希望があれば、できるだけ早めに業者へ伝えましょう。
10新築外構工事を依頼する際の流れとポイント
-
イメージの整理・要望のリストアップ
- ・「駐車台数は何台必要か?」
- ・「庭でガーデニングやバーベキューを楽しみたいか?」
- ・「防犯性やプライバシーをどれだけ確保したいか?」
-
複数の業者へ相談・現地調査依頼
- ・2~3社ほど声をかけ、プランや費用の相見積もりを取る。
- ・建築会社やハウスメーカーが提携外構業者を紹介する場合もあるが、比較検討が大切。
-
プラン提示・見積書の比較
- ・提案内容・デザイン・保証・アフターサービスなど総合的にチェック。
- ・価格だけではなく、業者のコミュニケーションや対応力も重視する。
-
契約・工事日程の調整
- 建物本体の完成スケジュールを考慮し、着工日を確定する。
- 近隣住民への挨拶を忘れずに行う。
-
施工開始・中間確認
- ・工事期間中は適度に進捗を確認し、疑問はすぐ相談する。
- ・変更点や追加工事が必要になった場合は、契約書の修正や追加見積もりを再度確認する。
-
完成検査・引き渡し
- ・契約時のプランどおりに仕上がっているかチェックする。
- ・傷や不具合の有無、保証書の受け取りも重要です。
11失敗しない業者選びのコツ
-
提案力・デザイン力を見極める
- ・過去の施工事例や写真をチェックし、自分の好みと合うか比較する。
- ・希望をしっかりヒアリングしてくれるか、提案の引き出しが多いかもポイント。
-
コミュニケーションのしやすさ
- ・打合せや報告を丁寧に行ってくれるか、対応がスピーディーかなどを要チェックする。
- ・外構工事は細かい変更や相談が多いため、相性が合う業者だと安心。
-
保証やアフターサポートの内容
- ・敷地や素材により、経年劣化や不具合が起こる場合がある。
- ・保証期間や定期メンテナンスの有無などを事前に確認しておく。
12【まとめ】最適なタイミングで、満足度の高い外構を
- ・おすすめの検討時期:建物着工が始まった頃(引き渡しまで3~6か月)
- ・メリット:打合せや見積もり比較に十分な時間が確保でき、建物との統一感や予算配分をしやすい
- ・後回しリスク:引っ越し後の生活に不便をきたしたり、予算不足で妥協が増える可能性も
外構工事は早めに計画すればするほど、理想に近いデザインと機能を実現できます。
「よくある失敗事例」や「補助金の活用」、「見積りチェックリスト」を押さえておくと、満足度の高い仕上がりを得られるはずです。
また、複数の外構業者から見積もりをまとめて取得できる一括見積もりサービス(例:エクステリアコネクト)などを利用すれば、価格や提案内容を比較検討しやすくなります。
ぜひ上手に活用して、安心かつ理想的な新築外構工事を実現してください。
「家の引き渡しは終わっているけど、外構(エクステリア)の工事がまだ…」
「住んでからじっくり外構を考えたいけど、生活への影響が心配」
新築住宅の計画では、どうしても建物の打ち合わせが優先されがち。結果的に、外構工事は「引き渡し後」「住みながら」進めるケースも珍しくありません。
実際、4割ほどの方が住み始めてから外構工事を行っているという調査もあり、必ずしも「引き渡しまでにすべて完成させる」必要はないのです。
本記事では、住みながら外構工事をするメリット・デメリットや、生活ストレスを軽減する工夫、子どもやペットの安全確保など、快適に進めるためのポイントをまとめました。外構を後回しにするか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
1外構工事は住みながらでも可能!

結論として、外構工事は新築の引き渡し後、住みながら進めても問題なく行えます。
ハウスメーカーや工務店ではなく、外構専門業者へ依頼する場合、工事の着手は引き渡し後となるのが一般的です。
引っ越しを早めたい方や、外構にこだわりたい方にとって魅力的な選択肢と言えます。
ただし、「住みながら工事」にはメリットだけでなく不便もあるため、事前にポイントを把握しておくことが大切です。
2住みながら外構工事をする5つのメリット
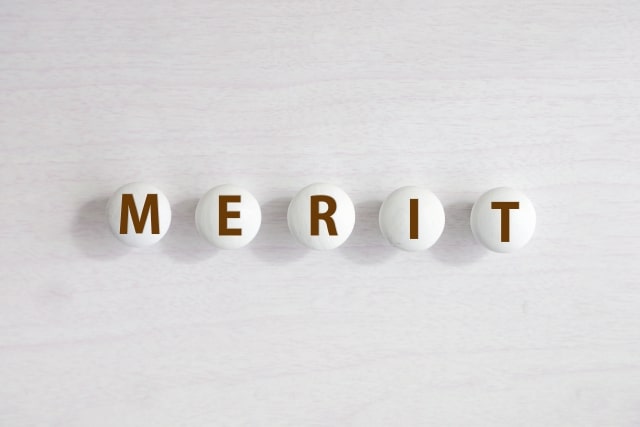
2-1. 専門業者を自由に選べる
- ・ハウスメーカー経由ではなく、外構の専門業者に直接依頼できる
- ・中間マージンが発生しにくく、費用を抑えながら質の高い工事を実現しやすい
- ・複数業者で相見積もりを取り、提案力や価格を比較検討できる
2-2. こだわりの外構をコストダウンで実現
- ・ハウスメーカーより1.3~1.5倍安くなるケースもある
- ・浮いた費用でグレードアップ(ウッドデッキ・カーポート等)が可能
- ・30~50万円安くなる場合もあり、建物に費用をかけすぎても調整しやすい
2-3. 実際に住んでみて使い勝手を確認できる
- ・暮らし始めて気づく課題(視線、照明不足、駐車場の配置など)をプランに反映できる
- ・生活動線を確認したうえで作る外構は満足度が高い
- ・プラン変更をスムーズに行いやすい
2-4. 引っ越し時期を早められる
- ・外構が未完成でも、建物の完成後すぐ入居可能
- ・天候や他工事の影響で外構工期が伸びても、引っ越しを遅らせる心配がない
- ・無駄な家賃や二重ローンを回避できる
2-5. 現場が落ち着いていて工事が進めやすい
- ・引き渡し後は外構業者のみが出入りするため、作業効率がアップする
- ・早ければ2週間前後で工事が完了する例もある
- ・工程が集中しすぎず、職人の質も安定しやすい
3住みながら外構工事をする5つのデメリット
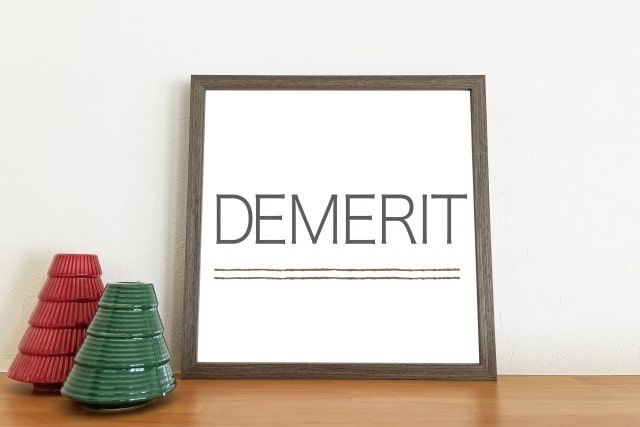
3-1. 引き渡し時の外観が未完成
- ・新居の引き渡し日に、外構ができていないため見栄えが半減する
- ・周囲が土のままだと新築の特別感が損なわれると感じる方もいる
3-2. 業者選定の手間
- ・外構業者は数多くあり、得意分野や価格帯がバラバラ
- ・時間をかけて情報収集・比較しないと、相場や業者の実力がわかりにくい
- ・一括見積もりサービスなどを活用する手もある
3-3. 予算不足になりやすい
- ・建物に資金を使いすぎ、いざ外構を依頼しようとした時に予算が足りなくなる
- ・結果的に最低限の工事しかできず、妥協ポイントが多くなる
3-4. 工事期間中の生活が不便
- ・駐車場をコンクリート舗装する場合、5~10日の養生期間は車を敷地に停められない
- ・工事騒音や泥汚れなどで、小さなお子様やペットがいると安全面・衛生面の不安がある
3-5. 後回しにして放置されるリスク
- ・引っ越し後の生活が忙しく、外構の計画が先延ばしになってしまう
- ・雑草が生い茂り、玄関周りが汚れやすいなど生活導線が悪化する
- ・結局手をつけずに長期間放置されるケースもある
4住みながら外構工事を快適に進める工夫
4-1. 生活ストレスを軽減する工夫
-
1. 洗濯物は室内干しを中心にする
工事期間中は土埃が舞うこともあるため、洗濯物が汚れる可能性を下げられます。
-
2. 玄関前に養生シートや人工芝マットを敷く
雨天時の泥汚れ防止に役立ち、靴や玄関ポーチをきれいに保てます。
-
3. 近隣のコインパーキングを事前に確認する
駐車場が使えない日数を考慮し、コインパーキングや月極の臨時利用を検討すると安心です。
4-2. 小さな子どもやペットがいる家庭向けの注意点
-
1. 工事エリア周辺に簡易フェンスやゲートを設置する
作業中に子どもやペットが現場に入らないよう、物理的に仕切りを作ります。
-
2. 作業時間帯を事前に業者と打ち合わせする
昼寝時間や家族の在宅ワーク中は騒音を避けるなど、生活スケジュールに配慮します。
-
3. 工具や資材の置き場をしっかり管理する
子どもが触れないように安全対策をしてもらうことが大切です。
5外構業者を選ぶ際のポイント
-
・職人の挨拶や近隣への配慮が行き届いているか
「住みながら工事」の場合、騒音・埃でご近所に迷惑がかかる可能性があるため、挨拶や周辺への気遣いが求められます。
-
・毎日の作業終了後に現場をきれいに片付けてくれるか
残材や工具を放置すると、転倒やケガのリスクが高まります。
-
・契約前に複数のプランや見積もりを比較する
相見積もりを行い、価格や提案力、対応の丁寧さを総合評価することが安心につながります。
-
・アフターサービスや保証内容を確認する
施工後の不具合やメンテナンス体制も重要なポイントです。
6費用・予算の具体例(目安)
「住みながら外構工事」でよく依頼される項目の費用目安は下記の通りです。
- ・アプローチのコンクリート舗装: 約10~20万円
- ・カーポートの設置: 約20~50万円
- ・フェンスの設置: 約10~40万円
これらはあくまで目安であり、素材・デザイン・施工範囲・地域によって金額は上下します。相見積もりで具体的な数字を出してもらい、比較・検討しましょう。
7住みながら外構工事をする際のローン・税金事情
7-1. ローンに組み込めるかの確認
- ・引き渡し前に建物とセットで外構も契約できれば、住宅ローンに一括で組み込みやすい
- ・引き渡し後に契約する場合は、リフォームローンや現金払いになるケースもある
- ・ハウスメーカーや金融機関に事前相談をする
7-2. 固定資産税への影響
- ・通常のフェンスやカーポートは固定資産税の対象外
- ・屋根・壁3面以上のガレージは課税対象となる
- ・外構工事の内容によっては評価額に影響するため、自治体の基準を確認する
8よくある質問
Q1. 引き渡し前に専門業者へ依頼することはできませんか?
一般的には難しいです。建物の所有権は引き渡しまでハウスメーカーにあり、外部業者が出入りすると責任範囲が曖昧になるため、引き渡し後に工事を開始する形が一般的です。
Q2. 工事期間はどのくらいかかりますか?
施工内容にもよりますが、2~4週間前後が目安です。カーポートや門柱、フェンスなど一通り行う場合は3~4週間、部分的な工事であれば1~2週間程度で終わる場合もあります。
Q3. 住みながら工事中、職人が頻繁に出入りするのは気になりませんか?
- ・職人は日中に作業するため、工事に慣れていることが多い
- ・作業時間帯や騒音・粉塵対策について相談が可能
- ・毎日の進捗確認ができるため、細かい要望を伝えやすいというメリットもある
9【まとめ】住みながら外構工事は十分アリ!でも事前計画が鍵
- ・4割以上の施主が「引き渡し後に外構工事」を行っており、メリットも多い
- ・ただし生活の不便や予算不足、騒音・プライバシー面などデメリットもある
- ・小さな子どもやペットがいる場合は安全対策を徹底し、ストレスを減らす工夫が大切
- ・業者選びでは、近隣配慮や施工後の片付け、アフターサポートなどもチェックする
外構は家の印象と暮らしの快適性を大きく左右します。住みながらの工事でも、早めに概算見積もりをとり、費用やスケジュールを明確にしておけば後悔なく理想的なエクステリアを実現できるでしょう。
「どこに依頼すればいいの?」と迷う方は、複数の外構業者から相見積もりを取れる「エクステリアコネクト」をぜひ利用してみてください。
ぜひ本記事を参考に、生活と予算にフィットした外構工事を進め、家づくりの“最後の仕上げ”ともいえるエクステリアを存分に楽しんでいただければ幸いです。