最短20秒で一括見積依頼!
実績のある地元の優良業者を
ご紹介いたします。
archive
イングリッシュガーデンや、アメリカの家の庭みたいな芝生の庭があったら…」なんて考える方も多いと思います。外構工事の一環で庭を芝生にする方も増えています。
しかし、どんな種類の芝があって、どういう手入れが必要で、いくら掛かるのか、人工と天然って何が違うのかなど、疑問だらけです。
庭を芝生にして「こんなはずじゃ…」と後悔する前に、少しでも芝のことを知って、やってよかったと思えるお庭にしましょう。
一見、同じに見える芝もさまざまな種類があります。それぞれ長所と短所があるので、自分の庭に適した芝を選ぶようにしましょう。
高温多湿の日本の気候に適した芝です。代表的な芝にノシバ・コウライシバ・ヒメコウライシバがあります。
・長所 … 夏の暑さや乾燥だけでなく、踏圧にも強い芝です。少ない肥料で育てることができます。
・短所 … 日本芝は種で増えることはありません。暖かい季節は青々としていますが、冬は枯葉色になってしまいます。(暖かくなると、再び色が戻ってきます)
ベントグラス類やブルーグラス類など、寒さに強く、冬でも芝が青い西洋芝は、主に関東より北の地域に適していますが、ダグラス類やティフトン類、ウーピングラブグラスといった一部の西洋芝は高温・乾燥に強く、冬は枯葉色になるので、関東より南に適している芝です。
・長所 … 種で簡単に増やすことができ、半日陰でも育てることができます。
・短所 … 高温多湿・乾燥に弱く、日本芝に比べ肥料の使用量も多く、芝刈りの回数が多くなります。
日本芝か西洋芝か、土地の整備が必要か不必要かによっても料金は変わってきます。
・すぐにでも芝が張れる場合 … ¥2,000/㎡
・土地が平らではなく、小石などの不純物がある、もしくは、現在、張ってある芝生を剥がす場合 … ¥4,000/㎡

出典:http://taka3.style.coocan.jp/
・すぐにでも芝が張れる場合 … ¥5,000/㎡
・土地が平らではなく、小石などの不純物がある、もしくは、張ってある芝生を剥がす場合 … ¥7,000/㎡
上記の値段は、あくまでも一例です。施工を依頼される際に参考にしていただければと思います。

出典:http://haku-s.blog.so-net.ne.jp/
芝の張り方によって費用だけでなく、雰囲気を変えることができますが、デメリットもあります。そちらを踏まえてデザインを決めるようにしましょう。
ベタ張り
隙間を空けずに芝を並べるので、一番手軽に芝生を楽しめる張り方です。
目地張り
一般的な張り方で、芝の間隔を3~4cm離して並べます。芝が均一になるまで3~4カ月かかりますが、芝の量は全面積の8割り程度で済みます。
十文字張り
目地が揃っているのできれいに見えますが、雨が降ったり、水が流れたりすると、目地に沿って土が流れやすくなるので、傾斜地には適していません。
筋張り
芝を筋状に張るので土の流出を抑えることができるので、傾斜地に芝を張る場合に適している張り方です。
市松張り
一見、芝の量が少ないので手軽に見えますが、その分、土を入れなければならず、後々、雨や水で土が流れてしまったり、芝が生えそろうまで時間がかかったりします。

天然の芝を使用した「天然芝」と、布やクッションなどの人工の素材を使用した「人工芝」素材が違うのは当然のことですが、それ以外に何が違うのでしょうか?

天然芝
人工芝とは違い「生きている」ので放置していると、丈が20cmぐらいになってしまい、病害虫を招いてしまいますので、頻繁に手入れが必要です。
また、年に数回の芝刈りや水やり、肥料やりは欠かせません。
人工芝
特別なお手入れは必要ありません。年数がたつと芝が寝てしまうので、細かい石をまくことで芝を起こします。

天然芝
しっかりと管理が行き届いていれば、何十年と保つことができます。
人工芝
使用環境にもよりますが、7~10年です。

天然芝
生きている芝にとって日照は、とても重要なので日当たりが悪い場所には向いていません。
人工芝
日照・広さに関係なく施工することが可能です。

初心者には難しいと思われがちな芝。しかし、しっかりと準備をしていれば、手間は掛かりますが難しいことはありません。ご自身で芝を張り、愛着がある庭にしてみてはいかがでしょうか?
※芝を張る前に
思い立ったらすぐにでも張りたいと思いますが、芝を張るベストな季節は根づきやすい3月~4月とされています。冬に芝を張っても芝は根付きません。3月~4月に張るメリットとして、根付きやすい以外にも、暑すぎず寒すぎないところもポイントです。人間が過ごしやすい季節が芝にとっても、いい季節と覚えておきましょう。

ホームセンターなどで10枚1束となって売っています。1束=1㎡が目安です。さまざまな種類の芝がありますが、初心者が育てやすく、手頃な値段なのはコウライシバ・ヒメコウライシバですので、そちらを選ぶといいでしょう。束の中に枯れている、根の厚みが薄い芝がまれに紛れていることがありますので、しっかりとチェックして選ぶようにします。

芝生の仕上がりの高さを決めます。土の高さは、仕上がりの高さマイナス15~20cmになるようにします。現状の高さを仕上がりの高さにしたいのであれば、すきとる必要がありますし、現状の高さより15~20cm高くなっても構わないというのであれば、すきとる必要はありません。

新しい土を入れます。水はけが良ければどんな土でも構いません。ただし、砂利が多い土は避けるようにしましょう。

芝生の仕上がりは、下地で決まると言っても過言ではありません。しっかりと整地していないと、芝を張り雨が降った際に水がたまったりして芝の生育に良くないので、しっかりと整地を行うようにします。一般的に水勾配は2%程度となっています。

下地の整地が終わったら、いよいよ芝張りです。建物を基準に芝を張っていきますが、進めていくうちに曲がってしまう場合があるので、定規代わりに紐を張っておくと、きれいな仕上がりになります。
障害物があるところは、余分な所をハサミでカットし形を合わせます。
芝が重なったり反ったりしていると、根付きが悪くなってしまうので、足で踏んだりして平らになるようにしましょう。

整地で使った砂を芝の上にかけていき、芝と芝の繋ぎ目、芝の隙間に土が入るようにならしていきます。目土をしっかりと入れると入れないとでは、根のはり具合が違います。

下地の土は新しい土ですので、ほとんど水分がない状態です。そこにも行き渡るようにしっかりと水やりを行いましょう。
芝生を長く楽しむためには、行き届いたケアが必要になります。住宅の環境、季節、芝の種類などを考慮して芝のケアをしましょう。

出典:http://shibafu.enjoy-gardening.com/
芝を張って1カ月程度は毎日、夏場は高温になりすぐ乾いてしまうので、朝と晩の2回まくようにしましょう。暑い日の昼間にまくと茹で芝となってしまうのでやめましょう。それ以外の季節は、芝の乾燥具合を見ながらまくようにしましょう。
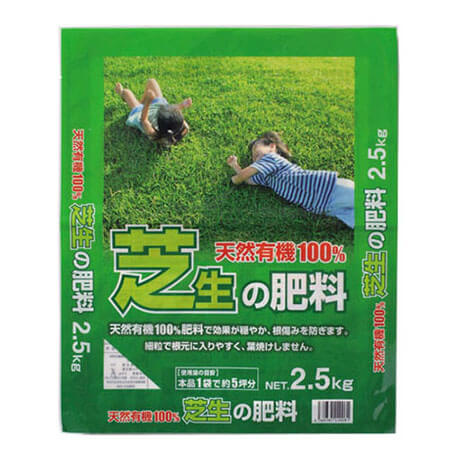
出典:http://www.kohnan-eshop.com/
芝生用の肥料を、成長期である4月~9月ごろに月1回程度与えるようにします。
芝が20 cm~25cmになったら刈るようにします。伸びてから一気に刈ってしまうと芝が弱ってしまいますので、注意が必要です。刈った芝は、掃除して取り除くようにしましょう。

常に生えてくるので、こまめに抜くしか方法はありません。芝生に映える雑草用の除草剤もあるので、そちらを利用してもいいかもしれません。

生育の悪い場所を中心に目土を掛けます。それによって成長を助けますが、地面の高さが高くなります。

害虫が出てくる前に先手で防虫剤を散布するようにします。それでも出てきてしまったら、早めに薬剤の散布を行うようにしましょう。
芝を張ってから2年目以降に10cm間隔で専用の器具で穴を空けて通気性と透水性を上げるようにしましょう。
芝生を長期間楽しむためには、これだけの手入れが必要となりますが、逆を言うと、これだけの手入れで芝生は長持ちするということになります。
どうしても自分で手入れが難しくなってきたら放置せずに、業者に依頼するなどして、きれいな芝生を楽しめる庭にしましょう。

緑にはリラックス効果があるといわれていますので、庭に芝の緑が加わるだけで雰囲気ががらっと変わってくると思います。ご家族はもちろん訪問される方も癒やされると思います。
天然芝か人工芝か、業者かD.I.Yにするかは、ご自身のお庭の環境や予算によって選び、ご自宅で芝の緑を楽しんでみてはいかがでしょうか。
せっかく芝生にしたのに、伸び放題、虫穴だらけ、芝生が寝きっているなんて嫌ですよね?自宅の環境、芝の種類を考えこまめなケアを怠らないようにしたいものです。
本当に芝を維持できるのか、自分ひとりでは不安だと思っている方は、
外構工事業者に住宅環境から適正な芝を判断してもらいましょう。
エクステリアコネクトでは、全国に優良工事店の登録があります。
お困りの方は、是非一度問い合わせてみてください。


タイルはマンションやビルの外壁、トイレやお風呂、床やカースペース、テラスといった使用できる場所が他の舗装材よりも多いことから、人気が高いといえます。
また、色が豊富にあるので、色を組み合わせたり、モザイクアートみたいにすることで、自分だけのエクステリアにすることも可能です。
タイルの値段は大きさや厚さ、使用する枚数、タイルの持つ特長(滑りにくい、雨に強いなど)によっても費用が変わってきます。また、モルタルやセメントは、おおよその値段なので購入する際、確認が必要です。
DIYでやった方が費用が10分の1に節約できますが、絶対に失敗したくないという方は、施工業者に依頼した方がいいでしょう。
施工箇所5㎡の場合
| DIY施工の場合 | 施工業者に頼んだ場合 | |
|---|---|---|
| タイル材料費 | 12,250円 | 60,000円 |
| 施工費 | なし | 100,000円 |
| 材料費 | 4,500円 | なし |
| 道具代 | 必要に応じて | なし |
| 合計 | 16,750円 | 160,000円 |

台所や洗面台、お風呂場といった水回りだけでなく、床をタイル敷きにすることで、ペットが滑りにくくなり、タイルを改良することで割れにくいタイルができ、カーポートにも使われています。また、外壁にも使われ今では、雨などによって勝手に汚れを落としてくれるタイルも登場しています。
近年では、タイル庭にテラスをつくる家庭も増えつつあります。
タイルも、ライフスタイルの多様化によってさまざまな変化がもたらされています。

出典:http://www.garden-shales.jp/
門扉と玄関を結ぶアプローチですが、どのような機能を持たせるとよいでしょうか?工事をした後に、「こんな機能を重視すればよかった…」と後悔しないためにも、前もって多くの方が重視されている機能を確認しておきましょう。
メリット
・傷に強くダニやカビの繁殖を抑えることができます。
・タイルは汚れや水分を吸収しないので、手入れの時間を短縮することができます。
・色が豊富なので、どの空間にも合わせることができます。
・他の建材にくらべ、維持費用(メンテナンス)がかかりません。
・色あせや変色がないので、いつまでもきれいなままです。
デメリット
・初期費用が、他の建材と比べ高くなってしまいます。
・モルタルを使用した施工の場合、養生期間のため他の施工にくらべると工期がかかってしまいます。※養生=モルタルやコンクリートを硬化のために保護すること
初期費用がかかってしまいますが、メンテナンスなどの維持費用が他の建材と比べかからないので長期的に見るとお得な場合もあります。また、工期も現在はモルタルを使用しない(湿式工法)で工期の短縮を図ることが可能です。

タイルの設置をDIYで行う場合、コンクリート面に薄いモルタルを塗って張り付けていく「直張り」と、モルタルで下地を作って叩きながら抑えていく「圧着張り」があります。
DIYで行う場合は、直張りで使用する「ポリマーセメント」の入手が難しいことや、下地で使用するコンクリートを高精度で施工しなければならないので、一般の方が行う場合、モルタルで高さを調整できるので「圧着張り」がおすすめです。
DIYで見落としがちなのが「下地の汚れ」下地に汚れがあると剥がれる原因になるのできれいにしておきましょう。
下地のコンクリートをきれいにしたら表面に吸収調整剤を塗ります。調整が終わったら、少しだけ水を混ぜたモルタルを敷きます。水練りしたモルタルですと、タイルが沈んでしまうので水の入れ過ぎには注意です。

モルタルを敷き終わったら、板などで表面をならします。この時点で水平を確認しておきましょう。

慣らし終わったら、いよいよタイルの張り付けです。セメントペーストのモルタルを、モルタルの上にこすりつけるように塗っていきます。乾いてしまうと施工がしにくくなるので、たくさん塗らないように気を付けましょう。
塗布したセメントペーストの上にタイルを置き、ゴムハンマーなどでセメントペーストとの面をくっつけます。叩き具合が甘いと裏側に隙間ができてしまい、強く叩くと沈んでしまうので注意しましょう。

固まったら、目地にモルタルを詰めて完成となります。
コツさえつかめば、タイル張りは難しくないと思います。
しかし、完璧に仕上げたいという方は、値段は張りますが施工業者に依頼するようにしましょう。
玄関まわりのタイルが汚れていると、家全体が汚れて見えてしまい、掃除が行き届いていないという印象を与えかねません。ップや雑巾掛けで落ちない汚れについては、専門業者にクリーニングを依頼するようにしましょう。

出典:http://www.keihangreen.com/
冷たさが感じにくいタイル、滑りにくいタイル、熱が伝わりにくいタイル、水に強いタイルなど、タイルにもさまざまな種類と特徴があります。しっかりと目的や用途にあったタイルを選ぶ必要があります。
目的や用途に見合うタイルを選び、長持ちするエクステリアにしましょう。
DIYでやる場合には、複数の色のタイルを使いオリジナルの模様を業者に依頼すると高く付くことがありますので、タイルで模様を造りたいという場合にはDIYでやることをおすすめします。
タイルには、さまざまな色や風合いを持つものがあり、タイル単体で眺めていると「この色良い!」とお気に入りの色彩のタイルが目に留まったりします。しかし思いの他、施工する場所の光や周囲の色彩とミスマッチだったりして「浮いて」しまうことも少なくありません。
また上に述べたように、屋内と屋外の別とか、雨がかりの有無とか、床面での使用か壁面での使用かなど、どういった場所でどういう用途で使われるかによって、採用できるタイル、採用できないタイルがあります。
そういった場合のために、ホームセンターにタイルを購入しに行く際には、施工する場所の写真を持って、イメージを膨らませながら購入を検討するとミスマッチが少なくなると思います。
その辺りも考えてタイルを選ぶようにしましょう。



株式会社こんぐみ設計事務所 一級建築士事務所 代表取締役 今 琢摩
一級建築士登録 第367808号
設計事務所、ゼネコン、内装施工会社等勤務を経て、株式会社こんぐみ設計事務所 一級建築士事務所を設立。
その時そこにしかないベストな空間を目指し、小さなプロジェクトでも大きな視野を忘れず、大きなプロジェクトでも小さな視点を忘れず、お客様のために全力を込めて当たることをモットーとする。
東京理科大学理工学部建築学科 卒業
株式会社こんぐみ設計事務所 一級建築士事務所
一級建築士事務所 埼玉県知事登録 (1)第11577号
https://kongumi.com/
幕末から明治にかけて日本に上陸したとされるレンガ。レンガというと、東京駅の外壁のような「赤レンガ」を想像される方が多いのではないでしょうか。あの赤い色は、粘土に含まれる鉄分が、焼かれる際に熱に反応して赤くなるもので、釉薬などを使って赤くしているわけではありません。
レンガを使った塀や庭を作ることをお考えの方で、積み上げればいい、敷き詰めればいいと安易に考える方もいらっしゃるかもしれませんが、意外とコツや経験が必要となります。
こちらは施工業者に依頼した場合のおおよその費用です。自分で施工(DIY)をお考えの方は、こちらを目安に必要なものを購入するといいでしょう。
レンガを花壇や門柱に使用する場合の費用
| 工事内容 | 内容詳細 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 基礎工事 | 積み高さ 地盤の状態により決定 |
3,000~8,000円/㎡ | 現地調査必須 |
| 組積工事 | CB120使用の場合 | 6,200円/㎡ | |
| 化粧目地積み | 化粧ブロック使用の場合 | 12,000円/㎡ | |
| アンティークレンガ積 | 門柱・花壇など | 29,000円/㎡ |

出典:http://azumazouendoboku.com/
昔は、建物や塀だけに使用されていたイメージが強いレンガですが、ガーデニングが盛んな現代では、殺風景な庭を洋風にアレンジするためにも使用されるようになりました。グルメな方はピザやパンを焼く窯、焼き物が好きな方は焼き窯を思いつかれたかもしれません。レンガは断熱性にも優れているので、こういった窯には最適です。
趣味が講じて庭に自分だけの窯を造られる方も増えています。

様々な場面で使用されるレンガですが、メリット・デメリットがあります。それらを知った上で、使用するようにしましょう。
メリット
・素材が土なので、環境に優しい
・厚さが約7cmあるので、外からの騒音を遮断することが可能
・1100℃以上で焼きあげられるので、断熱性に優れています
・経年変化によって味わいが出てくる
・コンクリートに比べ吸水率・保水率が高いので、植物の生育にも向いています
デメリット
・積み上げる際にモルタルで固めてしまっているので、簡単に変更することができない
・モルタルで接着するので手間がかかる
※地震に弱いと言われていたレンガですが、鉄筋などで補強することで、以前に比べると、剥落や割れの確率が低くなってきています。
花壇、塀、アプローチに至るまで、様々な場面に溶けこむレンガ。用途が多い割にそこまで費用もかからずに施工できます。
DIYなら自分好みに一からレンガを演出することも可能で、自分だけのエクステリアを演出することができます。

赤茶色というイメージが強い赤レンガですが、現在は、ブラウンやイエロー、ピンクといった様々な色が登場しています。また、実際に建物などで使用されたレンガもあり、こちらは経年変化により味わいのある色になっています。
一色で統一してもいいですが、様々な組み合わせにしてモザイクアートみたいにするのも、ひと味違った仕上がりになり、面白いかもしれません。
しかし、新品のレンガと違って、古いレンガは数が揃わないことがあるので注意が必要です。
エクステリアや塀造り、基本に忠実に行えばご自身で施工することも可能です。とはいっても、初めて行う方にとっては、相当苦労されるかと思います。「こういう感じなんだ」とコツを掴むためにも、小さいミニ花壇を最初に作ってみるといいかもしれません。
ある程度コツを掴んだら、「敷地の見取り図を描く」、「庭の日当たり状況を調べる(エクステリアの場合)」「使う資材や整地方法を考える」などした後に、自分の思い描く庭を設計図に書き起こしてから作業に入るようにしましょう。
自分で行う場合、デメリットでも記載したように、一度、モルタルで固めてしまうと簡単に移動することができません。ご自身で作業行う場合、作業途中で「イメージと違う…」とならないように、施工前から図面に起こすなど、仕上がりがイメージしやすいものを作りましょう。
また、レンガは吸水率が高くなっています。寒冷地で使用すると、レンガに染み込んだ水が凍って「凍結融解」を起こし割れてしまう場合があります。自分で施工する際はもちろん、業者に依頼する際も、使用するレンガを注意して確認するようにしましょう。

レンガを使用したエクステリアや塀造りといった簡単な作業であれば、ホームセンターで手軽に購入できるもので施工することが可能です。もちろん、プロのように完璧に仕上げるのは難しいかもしれません。しかし、基礎や施工がしっかりとしていれば、多少、レンガの目地が曲がっていても「オリジナル」のエクステリアとして楽しめるのではないのでしょうか。
現在、レンガも新品のレンガや中古のレンガ、様々な形をしたレンガなど多種あります。業者・DIY、どちらで作業することになっても、イラストに起こす、自分のイメージに近いものをネットで探すなどして、ある程度のイメージが出来上がった上で作業に入るようにしましょう。
レンガはエクステリアでも頻繁に登場する素材の一つです。そこまで高価なものでもないですし、時間が経つほど味が出て、自分のエクステリアが独自の色彩で彩られます。
エクステリアコネクトでは、レンガ工事に対応した優良工事加盟店が全国に複数いるので、早速、見積もりを出してみてはいかがでしょうか?


一言に「エクステリアに石を使う」に変更。といっても、自然の石をそのまま使うのか、割って使うのか、形を整えて使うのかなどさまざまです。「敷く」「囲む」「置く」「積む」といったアレンジの仕方によっても、庭の雰囲気が変わってきます。今はホームセンターなどでも手軽に手に入れることができるようになったので、好きな石を使って自分の庭をお好みの庭にアレンジしましょう。
使う石や立地条件、手数料の有無などによっても、施工費用は会社によって異なります。
乱張り
鉄平石 … ¥16,000/㎡~
イエローストーンなど洋風 … ¥13,500/㎡~
飛び石
自然石 … ¥3,500/個~
板石・加工品 … ¥2,500/個~
施工会社によっては、「石を何個以上使わないと割増」「何㎡以上じゃないと割増」という会社もあるようです。サイトなどに料金が記載されていない場合は、依頼をする前にしっかりと確認することが大切です。

石をエクステリアに使用する場合、先述にもあるように置く以外に「敷く」「積む」などの用途があります。
アプローチやテラスに敷き詰めれば洋風にアレンジもできますし、飛び石として使用すれば和風庭園にもアレンジできます。

舗装といえばこの2つの石が思いつくぐらい、敷石でよく使用されるこちらの石。市松敷きや短冊敷、煉瓦敷や四半敷きなど、さまざまな敷き詰め方がありますが、近年メジャーになっている敷き方が「乱張り」です。
不揃いの石を敷いていくだけなのですが、美しく見せるためには、「十文字目地にならない」「同じ大きさの石が平行に並べない」など、さまざまな注意点があり初心者にはなかなか難しい敷き方になります。
大きめの石を深めに埋め込み地面より少しだけ高くしたものです。歩きやすくなるだけでなく、地面が雨でぐちゃぐちゃになっていても飛び石を歩くことで靴が汚れることがありません。
真っ直ぐに並べた「直打ち」の他に「二連打ち」「三連打ち」「千鳥打ち」「雁
掛け」という並べ方がありますが、あまりくねらせると歩きにくくなってしまいます。
飛び石には、主に鉄平石や御影石を使用します。

外構に石を用いるときには、メリットとデメリットをしっかりと吟味し自分の庭園にあっているのかを考える必要があります。
メリット
敷石や飛び石は、雨の日でも靴が泥などで汚れないこと以外に、半永久的に使うことができ、雑草も生えにくくなります。また、和風・洋風庭園どちらの風景にもマッチし、明るくモダンな印象の庭にすることもできます。
デメリット
敷石・飛び石でのデメリットは、高額になるというところです。一つ一つ職人の手で並べていくので人件費がかかってしまうので業者に頼む場合、敷地の一部のみを頼まれる方がほとんどです。また、腕が良くても技術力が備わっていない職人に頼んでしまうと見栄えのいい仕上がりにすることはできません。
乱張りには「十文字目地にしない」「同じ大きさの石を並行に並べない」「通し目地を多く取らない」など決まりがあり、これらを行わないことできれいに見せることができますが、それらを完璧にこなし、きれいな乱張りに仕上げる職人は多くないといわれています。
逆に自分でやると費用は安く済みますが乱張りができるわけではないので、見栄えはきれいに見えないかもしれません。

敷石や飛び石に使われる石には、グレーやブルー、ピンクやイエローなど、多彩な石があるので、色を組み合わせによって重厚感のある仕上がりにしたり、和風・欧米風な仕上がりにしたりと、同じ敷石・飛び石でも、オリジナリティのある仕上がりにすることができます。
また、雨に濡れると表情が変わる石もあるので、買う前に濡らしてどんな感じになるのか見てみるといいかもしれません。

長年DIYをやっている人であれば、石を敷くことは造作も無いことだと思います。しかし、バランスとなると、本業としている方でも難しいとされているので、われわれがバランスよく仕上げるのは、もっと難しいと思われます。
多少バランスが悪くても自分で仕上げたいというのであれば問題ありませんが、絶対にきれいに仕上げたいというのであれば、乱張りや飛び石を得意とする業者に頼むといいでしょう。また、当然ながら石は重いのでご自身でやる場合は、腰など体を痛めないように気を付けましょう。
敷石は、敷くまでの工程が重要になってきます。下地を均等に固めてないと敷石が沈んでしまい均等な高さになりません。作業を行いながらしっかりと計測をやりましょう。また、何度も出ているように敷石はバランスが大切です。
石を張る前に、一度並べてみて上から眺めてバランスを整えるようにすると仕上がりがきれいになります。
エクステリアの中で敷石は張っていくだけなので、一見すると地味な作業に思えるかもしれません。しかし、完成すると雑草が生えにくくなり殺風景だった庭の風景も変わるので、気分も変わると思います。
そして、敷石・飛び石の仕上がりにはバランスがとても大切なので、自信がない場合は無理をせずに業者に依頼するようにしましょう。
石の外構工事を業者に頼むと、石の特殊な構造から高額になりがちです。DIY工事も可能ですが、見栄えが悪くなりがちです。安く、でも見栄えにもこだわりたいですよね?そんな時は複数の業者を比較してみましょう。
エクステリアコネクトでは、全国に優良工事店の登録があります。是非一度、お問い合わせください!


インターロッキングとは、インターロッキングブロックが略された言葉です。「インターロッキング」とは「かみ合わせる」という意味で、コンクリートやセメントを使うことなく、ブロックを互いにかみ合うような形状にして舗装します。
かみ合うことで互いに荷重を伝え合うので通常のコンクリート舗装にはない柔軟性があるとされています。
1950年代に西ドイツで生まれたインターロッキングブロックの技術は、1970年代に日本にも導入され、現在は一般道やショッピングモールなどに利用されています。

施工業者でばらつきはありますが、歩行用であれば、1㎡当たり¥7,000~¥9,000、駐車場(重量2t程度)用であれば1㎡当たり¥10,000~¥12,000当たりが相場といえます。
「1㎡の費用×広さ」以外に雨水溝や枡の工事などもありますので、若干多めにかかると見ておいた方がいいでしょう。他のエクステリア施工とは違いおおよその目安がつきにくい施工です。
ある程度自分で下調べをし、業者に依頼する場合は、いくつかの業者で相見積もりをするようにしましょう。
前述したように1970年代に日本に導入されたインターロッキングの技術は、当初は車道のみで使用されていましたが改良が重ねられ、現在では強度や耐摩耗性に加え、滑り抵抗性や耐久性、経済性にも優れていることから、現在では舗道や広場、公園やショッピングモール、遊歩道などさまざまな場面で見られるようになりました。
また、形状や色を用途に合わせてデザインが可能となったことから、近年では駐車場やアプローチといった、一般家庭でも見られるようになりました。

出典:http://g-ring5.blog.so-net.ne.jp/
インターロッキングは、コンクリートやセメントを使うことなく、一つ一つブロックをかみ合わせて並べなくてはならないので、すべて職人の手作業になります。そのため、コンクリートの舗装よりも割高になってしまいます。
ブロックを張るためには、下地作りが何よりも重要とされており、インターロッキング施工においての要とも言えます。インターロッキングでのブロックは完全に固定されていないので下地作りを怠ってしまうと、すぐに動いてしまいます。
よく、街なかで凸凹になったインターロッキングブロックを見かけると思いますが、あれは転圧を行わなかったなど、しっかり下地を造らなかったことが一因としてあります。
また、インターロッキングブロックの施工を完璧に仕上げることができる職人は多くありません。
難しいインターロッキングブロックの施工ですが、デメリットばかりではありません。レンガのように見えるインターロッキングブロックですが、レンガ舗装とは異なり、ブロック同士のかみ合いによって荷重を互いに伝えるので、レンガやコンクリート舗装にはない柔軟性があるとされています。
最近では色落ちしないブロックも登場してきているので、見栄えのある外構に仕上げることができます。

インターロッキングは、他のエクステリアと比べ大掛かりな作業となります。広い面積を施工する場合には、業者に依頼した方がいいでしょう。どうしても自分でやりたいという場合には、以下のことを留意して作業を行いましょう。

インターロッキングでは、コンクリートを一切使用しないので、土台となる下地(地盤)がしっかりしていないと、後になって表面が凸凹になってきてしまいます。しっかりと地盤・砂利面を転圧して締め固めるようにしましょう。

出典:http://smilehousekm.blog117.fc2.com/
透水性があり、地盤をしっかり固めていても雨水の浸透は地盤の動きによって凸凹した状態を作り出してしまいます。地盤が下がっても水たまりができない程度に地面に傾斜をつけるようにしましょう。

コンクリートやモルタルで固定していない分、経年変化によってインターロッキングにずれが生じてきてしまいますので、縁石などインターロッキングを固定するものが必要となります。

インターロッキングは、材料一つ一つの間に粒子の細かい砂をほうきで流し込むことで材料同士のぐらつきをなくし、砂によって材料同士を固定させていますが、最初の1~2年は雨によって内部の砂が流出してしまいます。その間は砂の補充が必要となります。

これまでの一般的なインターロッキングブロックは長方形でしたが、現在はさまざまな形が登場しています。色もグレーやブラウン、クリームなど豊富にありますので、希望する模様やご自宅の外観に合わせた形や色を選ぶようにしましょう。

何度も記述しているように他のエクステリア材とは違い、インターロッキングは施工業者にとっても難しい施工となります。
施工業者選びをしっかり行わないと、経年変化によって下地が沈んでくるといった理由で表面が凸凹になってくる場合があります。
どのエクステリアでも言えることですが、インターロッキングを理解しないまま業者に依頼すると、手抜き工事が行われたり、高額費用を請求されるおそれがあります。
業者に依頼する場合は職人の腕の良さだけではなく、しっかりとした業者かを確認するようにしましょう。
下地づくりは自分で行う際も重要です。他のエクステリアとは違いコンクリートやモルタルを使用しないので、しつこいぐらいに下地づくり(地盤固め)を行うようにしましょう。
ご自身で検索して分かると思いますが、インターロッキングを全面に出している施工業者は、まだまだ多くありません。それだけ技術を要するエクステリアと言えます。
そんなインターロッキングですから、自分の手で作り上げると他のD.I.Y以上に達成感が感じられると思います。しかし、あまり広い場所の施工は大掛かりなものとなり、デザインが崩れてしまうことも考えられるので、業者に依頼するようにしましょう。


コンクリートやタイル、ブロックやレンガなどのエクステリアとは違い、工事費用を安く抑えることができる砂利。
味気ないといった印象を持たれがちな砂利ですが、現在は、さまざまな種類や形、大きさの砂利が出てきており、ちょっとした工夫でおしゃれなエクステリアにすることができるようになりました。
外構工事に使用する砂利の費用
| 砂利を敷く面積 | 費用 |
|---|---|
| 10㎡ | 22,000円 |
| 15㎡ | 33,000円 |
| 20㎡ | 44,000円 |
これらはあくまでも相場ですので、使用する砂利の種類や施工する場所の面積、防草シートの有無、工事のしやすさなどによって費用は異なってきます。また、通販で安く売られていても、重量や数量によって送料が別途かかってしまう場合がありますので購入する前に必ず確認してください。

砂利には、「建材用砂利」と「化粧砂利」と大きく分けることができます。建材用砂利は、主にレンガなどを敷き詰める際に下地として地盤を固めるときに使用されます。
一方の化粧砂利は、ガーデニングやアプローチ、庭の通り道や植木鉢に敷き詰めて使用されています。形や見た目も整っており、使う砂利の種類や大きさによって洋風・和風どちらの雰囲気にすることも可能です。
近年では、人が歩くと音が出る大きめの砂利を家の回りに敷き詰め、防犯としても使用されています。

コンクリートや他のエクステリア材よりも費用が安いということで注目されがちな砂利ですが、他にもさまざまな利点があります。砂利を敷いておけば石の効果で雑草が生えにくくなります。
プラスアルファで砂利の下に防草シートを敷いておくことで、より一層の雑草対策が期待できます。また、上記にも記述したように大きな音が出る砂利石を家の周囲に敷くことで防犯対策にもつながります。
その一方で、庭に落葉樹などがあると掃除が面倒というデメリットもあります。また土の上に直接砂利を敷くと、同じ場所を人や車が通ることで砂利が土の中に沈下してしまったり雨などによって泥が付着しやすくなったりしてしまいます。
これらのデメリットは砂利を直接土の上に敷いた上で起きることなので、防草シートなどを敷いて防ぐことができます。

ひとえに「化粧砂利」といっても、その種類や形はさまざま。砂利を敷くお庭やアプローチをどのような雰囲気にしたいかによって色だけでなく大きさや形も異なってきます。
西洋風のお庭にしたいのであればブラウンやベージュ系、和風のお庭にしたいのであればグレー系がいいでしょう。
いずれにしても、しっかりとイメージを持って砂利選びを行うようにしましょう。
代表的な砂利と特徴を紹介致します。

三重県菰野地区で産出される古くから日本で使用されている天然の化粧砂利です。水はけや保水性に優れているので、主に敷砂利として利用されています。

中国産の白御影石を人工的に丸くした化粧砂利です。洋風・和風どちらのお庭にもてきしていますが、特に枯山水をイメージしたお庭に適しています。

出典:http://www.nihontamaishi.co.jp/
白い大理石の砕石を人工的に丸くした化粧砂利です。和風・洋風どちらにも適した玉砂利です。

碁石にも使われる石です。和風・洋風どちらの庭にも適していますが、三分以上の大きさであれば、防犯用の砂利としても使用することができます。また、雨に濡れると光沢が増す那智石は、八分以上の大きさになると和風のお庭がおすすめです。
これら以外にも大理石の砕石(マーブルクラッシュ)やこはく色や乳白色した石英岩の砕石(クォーツクラッシュ)といったカラフルな砂利、瓦屋レンガを再利用した環境保護に貢献した砂利も近年では登場しています。
見て楽しむ砂利以外に、歩くと音が出て不審者の侵入を防ぐ防犯用の砂利も注目を集めています。

コンクリートやレンガなどを使用したエクステアよりは砂利は費用も安く、砂利を敷くだけなのでD.I.Yは可能ですが、やはり防草シートや土砂の処理は素人では難しいので、D.I.Yで行うのは砂利を敷くのみにすることをおすすめします。

雑草防止のためにも砂利は有効ですが、土の上に砂利を敷いただけでは、砂利の上を人や車が通ることで沈んできてしまいます。雑草を防ぐ・砂利が沈まないようにするためにも防草シートを有効活用しましょう。
防草シートを敷く際の注意点としては、敷く前に雑草を「根本から」取り除き、土の中に硬いものがあれば取り除くなど、しっかりと整地をしておくことが大切です。ツル性の植物は除草シートの上に生えてくる可能性もあるので、シートを敷く前に除草剤を散布しておきましょう。防草シートは薄いと数年でボロボロになってしまうので、少し分厚めの物を買うようことをおすすめします。
雑草が生えないようにするには、太陽の光が届かない5~8cmの厚さに砂利を敷き詰めることが重要です。
砂利は敷き詰める厚さにもよりますが、1㎡当たり20kg入りで3~4袋程度の砂利が必要となります。
イメージしていた砂利と違うと思っても、一度敷いた砂利をやり直すのは大変面倒です。しっかりとイメージ作りをしてから、砂利を購入するようにしましょう。通販で砂利を購入する場合は、お試し用砂利が販売されている業者もありますので、自分のイメージどおりか迷った場合は、そちらをご利用するのもおすすめです。
砂利も昔に比べると、さまざまな色や形などが出回るようになりました。それに合わせるように防犯やエクステリアなど、さまざまな使われ方をするようになってきました。どこに砂利を使いたいのか明確にし、それに合わせた砂利を使用するといいでしょう。
また、近年では、瓦やレンガなどの廃材を利用した砂利も登場しています。景観が目的ではなく、除草を目的とした砂利の購入であれば、エコで環境にやさしいこちらもおすすめです。


駐車スペースの舗装にコンクリートを使いたいと思っている人も多いのではないでしょうか。しかし昨今はコンクリートの価格が上昇し「一体、いくらかかるの」と心配になることも多いようです。
今回は、コンクリート駐車場のメリットとデメリット、気になる費用から注意点までわかりやすく解説します。

コンクリートとは、セメントに砂や砂利、水を配合したものです。コンクリートで舗装された駐車場にはたくさんのメリットがあります。まずはメリットとデメリットをお話しします。
駐車場には、コンクリート舗装以外にもタイル張りや石張り、インターロッキングなどがあります。タイル張りや石張りは、家との調和がとりやすく高級感もありますが、コンクリート舗装と比べると費用が高くなります。また、石畳のような美しさがあるインターロッキングは除草の必要がありこまめなメンテナンスが必要です。
コンクリート駐車場は、必要最低限の材料で舗装ができるため経済的です。費用を抑えたい人にはピッタリでしょう。また、コンクリートはメンテナンスが楽です。日常の手入れは、ほうきではいたり、水で流したりするだけです。雪が降る地域では、雪かきもスムーズに行うことができます。除草の必要もなく施工時にしっかりと養生期間を設けることで強度も出すことができます。
駐車場の床に求められることは、車の荷重に耐えられることです。自家用車の重量は約1.8トンです。60kgの人が5人乗れば2トン以上の荷重になります。コンクリート駐車場は、必要な厚さと鉄筋を配置することで荷重に耐えられる構造になります。コンクリートの長所である「圧縮への強さ」と鉄筋の長所である「引っ張る力への強さ」を共存させることで丈夫な駐車場になります。
参考URL「FUKKO 透水性舗装仕上材」:https://www.fukko-japan.com/eco/dry-tech.html
コンクリート駐車場は、雨が降ったり洗車をしたりしても駐車場内に水がたまらないように排水勾配をとります。ただ、排水勾配がとりにくい場所であることも考えられます。その場合は、透水性舗装仕上材を使う方法もあります。透水性舗装仕上材とは、保水性と透水性をもつ材料です。コンクリート駐車場は、夏場は太陽の熱で高温になります。保水性のある透水性舗装仕上材を使うことで、打ち水効果が期待でき、駐車場や玄関前の温度上昇を抑えられるでしょう。
参考URL「フロアエージェント コンクリート刷毛目仕上げ」:https://www.fa-concrete.com/hake.html
コンクリート駐車場は、ツルツルの表面に仕上げるのではなく「刷毛引き仕上げ」が施されます。刷毛引き仕上げとは、生のコンクリートを敷きつめて、半がわきになってきたころにわざと刷毛を使って凸凹をつける仕上げ方法です。小さな刷毛目をつけることで物理的なすべり止めになります。また、刷毛目によって小さなヒビが目立ちにくくなります。
コンクリート駐車場にもデメリットがあります。それは、施工に技術が必要であることです。とくにコンクリート舗装は、はじめの施工が長く耐久性に影響を与えることが多く、施工の技術が満足度に直結します。また、個人の住宅の場合、コンクリートの無機的な感じが家の雰囲気と合わない可能性もあります。
つまり、個人宅でコンクリート駐車場を採用するためには、施工技術はもちろんですが、家や景観に合うデザインセンスも必要になります。さらに複数台の駐車場施工には、荷重に耐えられる施工技術も求められるのです。

コンクリート駐車場の工事費用はいくらくらいかかるのでしょうか。ここからは、車1台分のコンクリート駐車場(18㎡)を想定し、おおよその費用目安をお話しします。
ただし、昨今の世界情勢によりコンクリート価格や人件費が高騰しています。費用は一例とし、実際の金額は複数社から見積もりを取り寄せて検討することをおすすめします。
掘削と鋤取りは、駐車場にする地面を掘って削り平らにする作業です。費用は面積で変動し、1㎡あたり1,000円程度が相場でしょう。
掘削作業を行うと、処分する土が出ます。土は決められた処分方法があり、処分する土の量と土を運搬する距離によって費用は変動します。土の処分費用の相場は地域によってもばらつきがありますが、1㎡あたり1,000円程度が相場でしょう。一般的に移動距離が短い地方は安く、移動距離が長くなる都会は高い傾向があります。
コンクリート駐車場は、車の重たい荷重に耐えられなければなりません。そのため、平らにしたら砕石を敷いて転圧機で固く固めます。砕石を敷き詰める理由は、下地つくりと水はけをよくするためです。砕石は、大きな岩を人工的に壊して作られます。角がゴツゴツとしているため、転圧することで角と角がしっかりと組み合わさり、強い地盤になります。
砕石と転圧は1㎡あたり1,500円程度ですが、砕石を多く使った場合はもっとかかる可能性があります。
コンクリート駐車場の強度を保つために鉄筋を使います。鉄筋というと建物の中を通る棒のイメージですが、駐車場にはワイヤーメッシュと呼ばれる網状のものが使われます。そしてコンクリートを流し込むための型枠を設置します。
鉄筋と型枠の設置は、使うワイヤーメッシュや型枠の大きさによって変動しますが1㎡あたり1,000円程度でしょう。
型枠を設置したらいよいよコンクリートを流し込みます。コンクリートは、乾いてくると縮みます。縮むことでひび割れを起こすため、前もって目地とよばれる切れ目を入れます。目地は水はけをよくする役割もあります。目地は直線で規則的に入れることもできますが、エクステリアの一部として模様のようにデザインしてみてもステキです。コンクリート舗装は1㎡あたり8,000円から1万円程度でしょう。目地に別途費用がかかる場合は、1mあたり数百円~1,000円以内が目安でしょう。
コンクリート駐車場の費用は、他にも生コンクリートを運ぶミキサー車や人件費が必要です。人件費は、人数によって変動します。 車1台分のコンクリート駐車場(18㎡)を設置する工事費用の総額は、おおよそ30万円程度が目安になるでしょう。

コンクリートは品質が安定し、価格も手ごろなため駐車場の舗装に適した材料です。しかし、コンクリート駐車場施工の工程は「完成すると見えなくなる工程」が大部分を占めています。そして「見えなくなる工程」こそが「耐久性の要」となります。
コンクリート駐車場の外構工事の最大の注意点は、業者選びです。「ここが一番安いから」という理由で業者選びをしてしまうと「コンクリートの厚みが足りず、すぐにヒビがでた」という事態もあり得ます。
業者を選ぶときには、地元の気候や地域性を知り、見えない工程も信頼して任せられる業者を選ぶことが大切です。
コンクリート駐車場にはメリットとデメリットがあります。ただ、デメリットは信頼できる業者を選ぶことで乗り越えることができます。大切な車を守るためにも正しい施工と信頼できる業者を選んでみてはいかがでしょうか。


ブロック塀は、定番の塀です。人気の理由は、費用が安く使いやすいことでしょう。しかし一方で「ブロック塀の安全性が気になる」という人も多いのではないでしょうか。
今回は、ブロック塀の基礎知識とメリットとデメリット、そして気になる費用から補助金を受ける条件まで徹底解説します。

ブロック塀には大きく分けて3つの種類があります。
いわゆるグレーの昔ながらのブロック塀です。コンクリートブロック塀は、建築用の空洞ブロックを使い、鉄筋で補強します。「ブロック塀の安全性が気になる」という人は、鉄筋が正しく配筋されず、災害時に倒壊した例が思い出されているのではないでしょうか。しかし、法規を守り正しく施工されたブロック塀は構造的にとても安定しています。
ただし、コンクリートブロック塀はコンクリートの素材があらわになっています。ブロック塀の中では一番安い費用に抑えることはできますが、家との調和や景観との調和を考えると美しいとは言えないでしょう。
コンクリートブロック塀の美観を改善したものが化粧ブロック塀です。現場で仕上げる左官仕上げの塀よりも工期が短くできることが特徴です。ただし、建築用の空洞ブロックよりも費用は高くなります。またタイルのように目地が出ます。
化粧ブロックは、色や質感や形にたくさんの種類があり、和風にも洋風にも対応できるブロック塀です。
左官仕上げブロック塀は、コンクリートブロック塀を土台の壁として、左官で下塗りをし、さらに吹付けをした塀です。コンクリートブロック塀や化粧ブロック塀のように目地が出ないことが最大の特徴です。費用は現場での仕上げ作業がある割に安く、コスパのいい塀といえるでしょう。
ただ、最近の家の外壁には工期が短いサイディングが使われるようになりました。養生が必要な吹付け作業は工期が長くなる一面もあります。

ここからは、ブロック塀のメリットとデメリットをお話しします。どちらも知っておくことで、より適した塀を選ぶことができるでしょう。
ブロック塀最大のメリットは、プライバシーが守れることです。ブロック塀には透過性が全くないため、視界をシャットアウトすることができます。
プライバシーを守るためには、人の目の高さである1.5mが必要と言われています。建築基準法では、コンクリートブロック塀の最大施工の高さは2.2m以下と定められているため、目隠しとしての高さも確保することができます。
ブロック塀の耐久年数は30年ともいわれています。木材のように腐ったり、スチールのように錆びたりする心配もありません。正しい施工がされているブロック塀ならば、簡単なメンテナンスをするだけで長く使うことができます。
ブロック塀に使われるブロックは、大量生産ができる素材です。そのため、単価が安くなります。また、ブロック積み作業は、大きな重機を使わず比較的小回りがきく作業です。使い勝手がいいことも大きなメリットです。
ブロック塀は視線だけでなく風や光も遮断します。とくに防犯性を高めるために高さを出した場合は、風通しと日当たりのデメリットが大きくなる可能性があります。ただ、風が強い地域では、風よけとしてブロック塀が使われることもあります。 風通しと日当たりのデメリットを解消するためには、部分的に透かしブロックやフェンスを使う方法があります。透かしブロックとは、スクリーンブロックとも呼ばれています。
参考URL「北陸エクステリア スクリーンブロック」:https://hokuriku-ex.co.jp/?catid=92&itemid=1335
無機的なブロック塀のアクセントにもなり、適度に光と風を通します。ただし、透かしブロックやスクリーンブロックを組み合わせる場合は、鉄筋の連続を妨げる可能性もあります。取り入れるときには、耐久性に影響を与えないデザイン計画が必要です。
一定の高さを超えたブロック塀は圧迫感があります。圧迫感を解消するためには、塀をブロック積みだけで構成するのではなく、ブロック塀にフェンスを組み合わせる方法があります。また、ブロック塀にスリット(隙間)をつくることで抜け感を出すこともできます。
参考URL「庭工房 スリット入りブロック塀例」:https://www.niwakobo.jp/works/w_style/w_natural/kyoukaiburokkubei.html
ブロック塀のメリットは、使い勝手のよさですが「簡単に使えてしまうこと」がデメリットになることもあります。大きな地震が起きたとき、倒壊したブロック塀をニュース映像で見たことはありますか。あれらのブロック塀倒壊は、安易な施工が原因です。ブロック塀は、正しい施工が必須条件です。
ブロック塀の正しい施工は「基礎工事」「配筋」「控え壁」など基本的な事項が建築基準法に明記されています。ブロック塀を安全に施工し長く使うためには、正しい施工ができる業者を選ぶ必要があります。
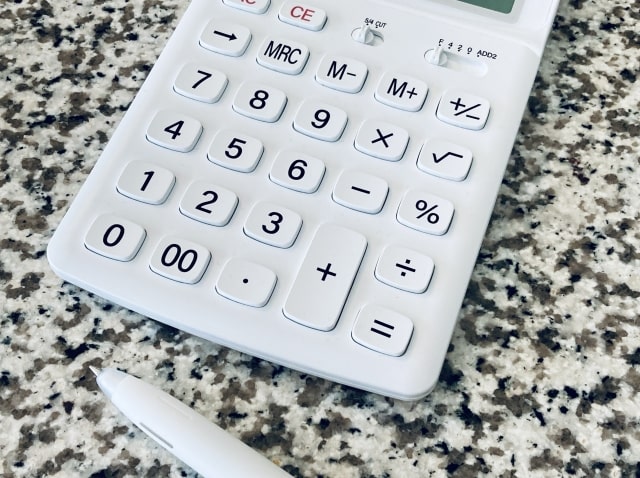
ブロック塀設置には、ブロック材の費用だけでなくさまざまな費用が必要です。ここからは、設置までに必要な費用を細かく説明します。
掘削工事とは、ブロック塀を設置する場所を掘り、基礎をつくるための下準備です。掘る深さは設置する塀の高さによって変わります。土を掘る作業のため、掘る作業費用と掘った土を移動処分する費用がかかります。
費用は面積によって変動します。一般的な戸建ての場合は3万円ほどかかり、残土処理に別途費用がプラスされることもあります。
掘削をしたら砕石を敷いて転圧をします。転圧は塀が完成すると見えなくなる作業ですが、ブロック塀を安定させるための大切な工程です。コンクリート基礎工事は、掘削した基礎部分から塀の予定高さまで縦筋を組み、コンクリートの基礎を打つ作業です。
基礎工事費用も面積によって変動しますが、おおむね1㎡あたり2万円程度です。
縦筋の間にブロック材を積み上げる作業がブロック積みです。ブロック積み費用は、1㎡あたり1万円から15,000円が一般的ですが、人手不足の影響から高騰しつつあります。
もしも、古いブロック塀があり撤去する必要がある場合は、既存構造物撤去工事費用がかかります。1㎡あたり1万円程度です。
ブロック塀設置までの費用総額は、選ぶブロックや面積によって変動します。例えば、戸建て(130㎡の土地)の周囲すべて(約46m)を囲うとなれば基礎工事費用も含めて80~150万円かかります。家の周囲すべてを塀で囲う可能性は低いですが、予算は多めにとっておくほうが選べる範囲は広くなります。

「うちのブロック塀を修理したいけど費用が心配」という人もいます。実は、倒壊のリスクがあるブロック塀の修理には自治体から補助金が出る可能性があります。 補助金の対象になるブロック塀には、いくつかの条件があります。1つ目は「道路に面していて通学路や避難路に面していること」です。2つ目は「高さが高かったり薄かったりして災害時に倒壊するリスクがある」です。3つ目は「ひび割れや傾きがある」です。4つ目は「築30年以上」です。5つ目は「鉄筋が通っていない」「コンクリート基礎工事がされていない」です。自治体によって条件や対象の範囲が違うため、検討するときには自治体に確認をしてください。
ブロック塀は、手軽でコスパのいい塀ではありますが、正しい施工が必須条件です。とくに敷地外との境界線にもなるブロック塀は万が一倒壊したときには大きな被害に繋がります。災害が起きる前にブロック塀の見直しと正しい施工を検討してみてはいかがでしょうか。


外構のスタイルは「オープン外構」「セミオープン外構」「クローズ外構」の3タイプに大別されます。セミオープン外構は、セミクローズ外構とも呼ばれ、オープン外構の良さとクローズ外構の良さを併せ持つ、まさにいいとこ取りの外構スタイル。
我が国で最も多く採用されているのがこのセミオープン外構です。では、セミオープン外構を選択する利点と注意すべきポイントとは一体何でしょうか。
当コンテンツでは、これからセミオープン外構を検討されている方に向けて、選択する上でのメリットとデメリットを順に解説します。

出典:http://www.atlas-home.co.jp/
オープン外構のように完全に開かれた外構ではなく、クローズ外構のように完全に閉じた外構でもないデザインです。例えば、塀やフェンスは設けるものの、比較的低めに抑えたり、部分的に設置したりするなどして、解放感あるデザインを重視。
あるいはカーポートは開放的に、門周りはクローズにするなど、オープンなエリアとクローズなエリアを分ける考え方もあります。プライバシーやセキュリティは高めつつ、解放感も取り入れるという設計思想です。

出典:http://asunaro-fujieda.com/
セミオープン外構は、オープン外構の良さと、クローズドスタイルの良さを同時に持っているのが魅力です。具体的に見て行きましょう。

完全に閉じるのではないので、ある程度の解放感があり、近隣や地域住民との自然な交流も広がります。ガーデニングをしていると、自然に声を掛けられ、お友達の輪が広がって行くのも、程よい解放感があればこそ。地域の一員として自然に溶け込むことができる外構です。

必要な部分に限定してフェンスや門扉などでガードすることで、プライバシーや防犯性能を高めることができます。オープン外構では住宅だけで防犯やプラバシーを守りますが、外構でガードする事で二重の自衛が可能になります。

フェンスも塀も作らないオープン外構と違い、フェンスや塀で住まいを素敵に演出できます。飽きたら新しいデザインを取り入れながら、外構自体を楽しむことができます。部分的な工事で済むのでコストがかさまないのも魅力です。

オープン外構の良さも、クローズドスタイルの良さも持っているのがセミオープン外構ですが、一歩間違えると、両方のデメリットを併せ持つ外構になる危険性もあります。まずは、その危険性を理解しておきましょう。

解放感はオープン外構には及ばず、プライバシーやセキュリティではクローズ外構にはやはり及びません。いいとこ取りのつもりが、解放感がなく、プライバシーやセキュリティも中途半端な機能しか持たない外構になりかねません。
設計段階から、施工会社などと充分に話し合う事が大切です。

フェンスも門も作らないオープン外構に対し、セミオープン外構は若干外構費用がアップします。重装備のクローズ外構ほどではないものの、ある程度のコストを見込んでおく必要があります。

何事も極端を嫌う日本では、セミオープン外構はとても人気のある外構です。それは、近隣と上手に調和を保ちながら、家族の安全やプライバシーも守りたいという知恵を備えているためとも言われています。次のような方は、セミオープン外構がお奨めです。

プライバシーや防犯の観点から、塀やフェンス、門扉などでしっかり自衛したい。同時に、隣近所や地域の人々との交流も大切にしたいという方にお奨めです。重厚すぎる壁や塀は下手をすると近隣との交流の「障壁」になる事もあります。家族の安全は守りつつ、ふれあいや交流も大切にしたいという方にピッタリなスタイルです。

オープン外構は洋風の街並みに調和し、クローズ外構は都市部や和風の街並みに調和します。街区が統一されたデザインでない限り、様々な様式の住宅が混在した街並みになるため、どんな街並みにも調和するセミオープン外構なら、違和感なく溶け込むことができます。

セミオープン外構は、オープン外構の良さと、クローズ外構の良さを併せ持っています。どうせ暮らすなら、両方の良さを取り入れたいという欲張り派にもお奨めです。
オープン外構とクローズド外構の“ハイブリッド外構”とも言えるのが、セミオープン外構です。上手く設計すれば“いいとこどり”になりますが、一歩間違えると“どっちつかず”の中途半端な外構で終わる危険性もあります。
設計に当たっては外構工事会社に任せっきりにせず、セミオープン外構の長所・短所を把握したうえで、しっかり話し合う事がポイントです。


家の外構工事を検討する際によく見かけるキーワード「オープン外構」。このオープン外構とは、道路との境界線を塀や門扉で囲わないものの事を指し、欧米諸国に特に多いエクステリアのスタイルで、明るく開放的なのが魅力です。
芝生やタイル、石張りなどで敷地を示すものや、花壇や低い植え込みで境界線を示すものなど様々なスタイルがあります。接道する公道や私道と私有地を遮るものがないので、道行く人に自慢のお庭を存分に楽しんでもらいたいという方などが好んで採用しています。
そのためオープン外構は、敷地面積が広く隣接するお宅との間隔にゆとりがあるような地域や、人々との交流を大切にしたいという方にお奨めのエクステリアプランです。

敷地の境界線すべてを開放的にするというのではなく、あくまでも道路から建物や庭が見通せる事が基本となります。隣家との境界にフェンスや塀を設けたとしても、道路に面して開放的な場合はオープン外構と言えます。
また、開放的と言っても何も設けないというのではなく、最小限の樹木で家の中を見えにくくしたり、低い植え込みで敷地内に立ち入りにくくしたりと言った工夫は行うのが普通です。
解放感は大切にしながらも、必要なプライバシーや安全性は守るというのが、日本的な考え方と言えます。

道路との間に遮蔽物を作らないオープン外構は、いわば「見せる(魅せる)外構」です。近隣住民や通行人に、美しい庭や住宅を楽しんでもらうという他に、住まい手にもいくつものメリットがあります。具体的に見て行きましょう。

塀やフェンスで囲われていないため、のびのびとした解放感が感じられます。道行く人に建物やお庭を楽しんでもらえるため、街の景観に貢献する外構とも言えます。道行く人との交流が自然に広がるもの魅力です。

敷地が狭く、玄関アプローチやカーポートに充分なスペースが確保できない場合、無理に門扉やフェンスなどで仕切らず、オープン外構にした方が圧迫感はありません。また、庭が狭い場合も無理に塀などで囲わない方が、庭を有効に使えます。

塀やフェンス、門扉などを使わないため、外構工事費が抑えられます。道路に面している距離が長いお宅ほど、大きなコストダウンになります。

出典:http://www.fukujuen-ex.com/
開かれた外構であるという事は、注意すべきポイントもあります。それらの留意点を把握したうえで適切な備えをしておくことが大切です。主な留意点は以下のようなものが挙げられます。

塀やフェンスがない分、敷地内に侵入しやすくなります。不審者に限らず、犬や猫の糞のトラブル、ゴミの投げ入れなども心配されます。大事なお花が折られたり、盗まれたりといった問題も発生しがちです。防犯カメラを設置して、トラブルを防止する方法もあります。

家族の安全とプライバシーは外構ではなく住宅で守るという発想が必要です。道路からは見えにくい位置にリビングや浴室を配置したり、防犯グッズを二重‣三重に設置したりと言った対策を取っておくことがオープン外構には重要です。

道路との境に全く障害物がない場合、お子様がボールなどを追って道路に飛び出してしまう恐れもあります。同様にペットが飛び出さないよう、しっかり管理する必要もあります。交通量の多い立地の場合は慎重な検討が必要です。

欧米では主流のオープン外構にも、メリット・デメリットがあります。オープン外構を採用するかどうかは、メリットを優先するか、デメリットを問題視するかで決まってきます。以下のような方にはオープン外構がお奨めです。

不審者は家の周囲の身を隠せる場所を探して、そこから侵入します。従って、塀で囲まれ外部から目が届きにくい家は格好のターゲットとなってしまいがち。一方、オープン外構は外部から丸見えになる分、不審者には侵入しづらい家と言われます。開放的な方がかえって安全性を担保しやすいと考える方にはお奨めです。

オープン外構は、道行く人にも建物やお庭を楽しんでもらえるエクステリアデザインです。自分だけで楽しむのではなく、いわば街の共有財産として、景観づくりに貢献しながら暮らしたいという方にピッタリです。逆に、それだけきちんと手入れをし続ける必要があるとも言えます。
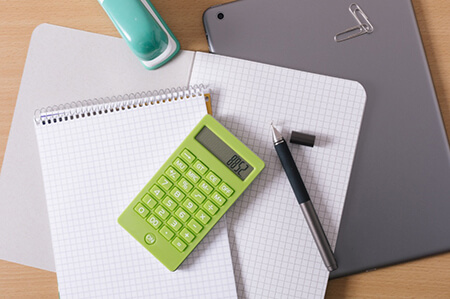
外構工事は多くの資材を使うため、想像以上にコストがかかるものです。新築時など、予算に限度がある場合にはオープン外構を検討しても良いでしょう。予算に余裕が出来てから必要に応じて追加工事をして行く方法もあります。
明るく開放的なオープン外構は、年々人気が高まっています。しかし、防犯やプライバシーの面では留意すべき点もあるため、設計の段階で充分な対策を取っておくことが大切です。
明るく開放的なオープン外構は、年々人気が高まっています。しかし、防犯やプライバシーの面では留意すべき点もあるため、設計の段階で充分な対策を取っておくことが大切です。




複数業者に相見積りで
失敗しない外構工事を!
最短20秒で一括見積依頼!
実績のある地元の優良業者を
ご紹介いたします。